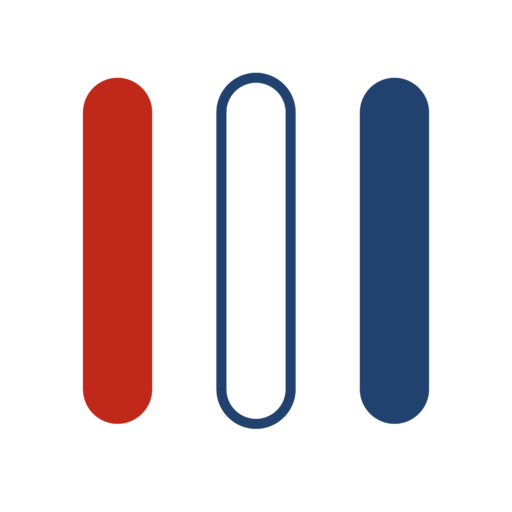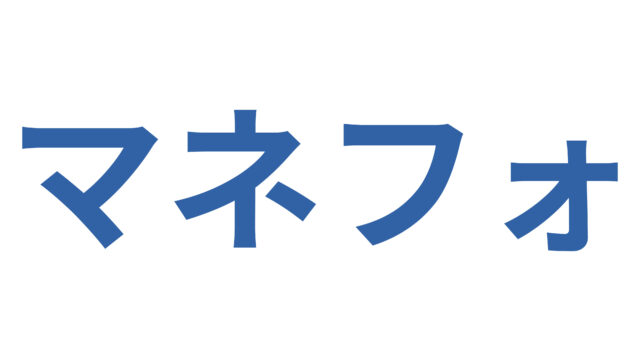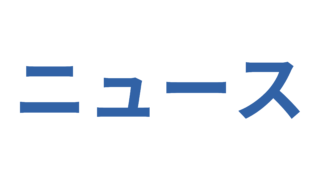*この情報は2023/12/13時点の情報に基づき記載しています。
・事業を行っていない法人
・事業を廃止する予定の法人
こんにちは、厚木市の税理士岩本隆一です。
今回のお話は
休眠会社
のお話です。
休眠会社とは
休眠会社とは、少なくとも
1年間は全く事業を行っていない
会社です。
売上や経費が発生しないことはもちろんのこと、預金の動きすらない状態をいいます。
会社法的には「12年間全く動いていない法人」が休眠会社の定義だそうですが、一般的には1年程度動いていなかったら休眠と考えていかなと思います。
休眠させるメリット
事業がうまくいかず会社を動かせない場合には、下記の選択があると思います。
・そのまま会社を存続させる
・会社を解散する
・会社を休眠させる
これら方法を比べた場合に、会社を休眠させるメリットは
・事業を再開するときに、休眠会社を使える
・均等割を免除される
・解散のための費用がかからない
の3つです。
「事業をまたやりたくなった!!」というときに会社を解散させていたら、新しく会社を作らないといけません。
また、事業を行っていなくても、そのまま会社を存続していると約7万円の均等割を支払わないといけません。したがって、「会社を動かしていないのに均等割を払いたくない!!」と思う人にも休眠がおすすめとなります。
そして、解散するためには費用がかかります。具体的には、解散登記には約40,000円+司法書士報酬、解散することを公に発表する公告には約30,000円、税務申告のための税理士報酬などがかかります。
*均等割については、東京23区は免除されませんので注意が必要です。
手続き
休眠会社とするためには、下記の書類をそれぞれの行政機関に提出します。
| 提出先 | 提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 税務署 | 異動届出書 給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書 | 全事業者 |
| 都道府県事務所 | 異動届出書 | 全事業者 |
| 市町村 | 異動届出書 | 東京23区以外の事業者 (東京23区は都に届出すればOK) |
| 労働基準監督署 | 労働保険確定保険料申告書 | 従業員がいる場合 (役員だけの場合は不要) |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所廃止届 資格喪失届 | 従業員がいる場合 (役員だけの場合は不要) |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 資格喪失届 | 社会保険に加入している場合 |
休眠中でも納税は発生するの?
休眠中でも会社が払わないといけない税金は、基本的には
ありません。
ただし、固定資産を保有している場合には固定資産税が発生します。
また、自動車を保有している場合にも、自動車税は発生しますので注意が必要です。
*法人が東京23区にある場合には、住民税均等割(70,000円)は必ず納付しないといけません。
休眠中にしないといけないこと
税金の申告
休眠中でも税金の申告は行わないといけません。
「なんで会社が動いていないのに申告しないといけないんだ!!」と感じるところですが、会社自体は存続しているので、たとえ全く動いてなくても、申告義務は消えないこととされています。
ただ、申告書自体は簡単に作れます。
税務署、都道府県税事務所、市町村役場に行き、「休眠をしているんだけど申告書の作り方を教えてほしい」と窓口に伝えれば、その場で教えてくれることでしょう。
この際には前年の申告書を持っていきましょう。
登記
株式会社の場合には、休眠中でも、役員変更登記が必要になります。
*有限会社や合同会社は必要ありません。
役員を変更しないといけない期間は定款に定めてあります。例えば、定款には下記の記載があります。
第25条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
日本公証人連合会
ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
変更登記をしないとどうなる?
登記を変更しない場合には、最後の登記から
12年
経過している会社については、法務局が法人を
抹消
する手続きを行います。(法務局)
なにも動いていない法人を残しておいても、法務局にとっては管理に手間がかかるし、犯罪に使われる可能性もあるので、消し去りたいということですね。
一応、会社に対して、「このままだと法人を抹消するよ」という通知書が登記所から送付されますので、知らぬ間になくなっているということはありません。
*有限会社や合同会社にはこの制度は適用されません。一定期間で必ず登記しないといけない事項がないからでしょうね。
まとめ
今回は休眠会社について説明しました。
少なくとも下記の二点は頭にいれてください。
・休眠すると均等割を払わなくていい(東京都以外)
・休眠しても確定申告は行わないといけない
今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。