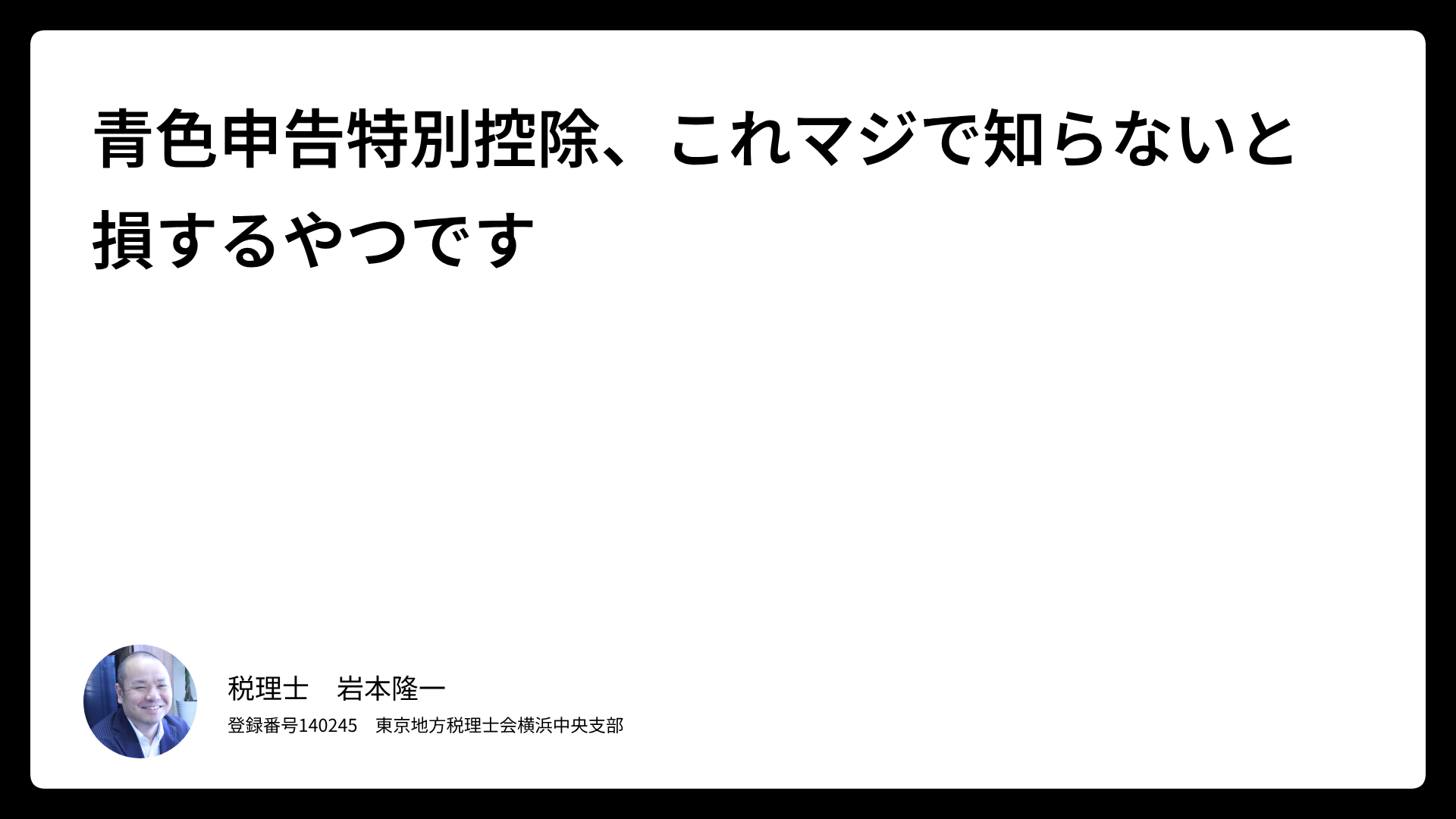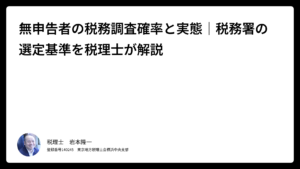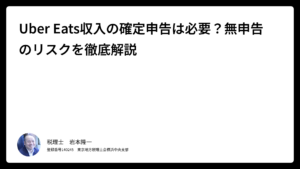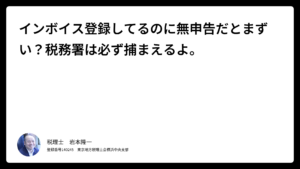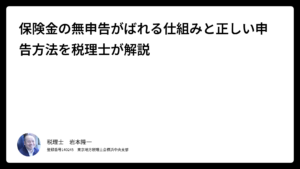毎日いろんな税金の相談を受けてるんですが、今日は青色申告特別控除について書いてみようと思います。
さて、これはフリーランスや個人事業主の方には超重要な話なんです。しかしながら、意外と「なんとなく知ってるけど詳しくは…」って人が多いんですよね。そこで今回は、この制度について詳しく解説していきます。
そもそも青色申告特別控除って何?
まず基本的なところから説明すると、簡単に言うと「ちゃんと帳簿つけて申告してくれたら、税金安くしてあげるよ」っていう国からのご褒美制度です。
ここで重要なのは、この控除は実は3段階あるということです:
- 10万円控除
- 55万円控除
- 65万円控除
おそらく「えっ、55万円?聞いたことない」って思った人、いると思います。というのも、実は2020年から変わったんですよ。

青色申告特別控除の要件と計算方法
それでは、各段階について詳しく見ていきましょう。
10万円控除
要件:
- 青色申告承認申請書を提出済み
- 簡易簿記でOK(家計簿レベル)
計算: 所得金額から一律10万円を控除
例)事業所得が200万円の場合 → 200万円 – 10万円 = 190万円(課税所得)
まず、これが最も基本的な控除です。実際、一番ハードル低いです。なぜなら、白色申告から青色申告に変えるだけで、税額が数万円変わることもあるからです。
55万円控除(複式簿記)
要件:
- 複式簿記で記帳
- 貸借対照表と損益計算書を添付
- 期限内申告
計算: 所得金額から55万円を控除(ただし所得金額が上限)
例)事業所得が300万円の場合 → 300万円 – 55万円 = 245万円(課税所得)
一方で、次のレベルがこれです。確かに10万控除と比べてだいぶハードルが上がります。とりわけ複式簿記をやらなくちゃいけないっていうのは厳しいですよね。
65万円控除(e-Tax申告 or 電子帳簿保存)
要件:
- 55万円控除の要件を満たす
- かつ以下のいずれか
- e-Taxで申告
- (誤解を恐れずに言えば)電子帳簿保存法に対応した会計ソフトで帳簿保存
計算: 所得金額から65万円を控除(ただし所得金額が上限)
そして最後に65万控除です。
なお、当然ながらe-taxを使って65万円控除を受ける人が多いですね。ちなみに、逆に私は電子帳簿保存の方で65万円控除を使ってる人を見たことはないです。
青色申告特別控除の勘違い
さて、ここからは実際によくある勘違いについて説明していきます。
勘違い①「65万円控除 = 65万円分税金が安くなる」
まず最初に、これが最も多い勘違いです。本当によく聞かれます。「65万円控除だから、税金が65万円安くなるんですよね?」って。
ところが、残念ながらこれは間違いです。
正しくは:
- 65万円控除 → 所得から65万円を差し引く
- 税率10%の人なら:65万円 × 10% = 6.5万円の節税
- 税率20%の人なら:65万円 × 20% = 13万円の節税
すなわち、控除額 = 節税額ではないんです。
勘違い②「いつでも65万円控除を受けられる」
続いて、「青色申告にしたから自動的に65万円控除でしょ?」これもよくある勘違いです。
しかし実際には、65万円控除には厳格な条件があります:
- 複式簿記での記帳
- 貸借対照表・損益計算書の添付
- 期限内申告
- e-Tax申告 or 電子帳簿保存
したがって、簡易簿記だと10万円控除止まりなのです。
勘違い③「期限後申告でも65万円控除OK」
最後に私から見て一番もったいないパターンです。実は、期限後申告になると、どんなに完璧な帳簿をつけていても10万円控除に格下げされてしまいます。
青色申告特別控除の節税効果
では、具体的にどれくらいの節税効果があるのでしょうか。
所得税率10%、住民税率10%の人の場合:
- 10万円控除:年間約2万円の節税
- 55万円控除:年間約11万円の節税
- 65万円控除:年間約13万円の節税
言うまでもなく、所得が高い人ほど節税効果は大きくなります。
私が考える「正しい会計」の重要性
ここからは、他の税理士があまり強調しない話をしたいと思います。
会計ソフトも完璧じゃない
「会計ソフト使ってるから大丈夫」って思ってる人、多いですよね。ところが、実は会計ソフトも間違えることがあるんです。
よくあるパターン:
- 勘定科目の自動仕訳が間違っている
- 期末の決算仕訳が漏れている
- 減価償却の設定ミス
要するに、大事なのは「ちゃんと会計のルールに則って処理すること」。私がいつもクライアントに言うのは「適当にやらないこと」です。加えて、会計ソフトに頼り切らず、最低限の会計知識は身につけておくべきです。とくに複式簿記で65万円控除を狙うなら、なおさらです。
正直、まだまだ多い「青色申告特別控除を受けていない」人たち
率直に言って、私のところに相談に来る人を見ていて感じるのは、「青色申告特別控除を受けていない」がまだまだ多いということです。これ、本当にもったいない。
実際に、私がクライアントを見ていて思うのは、白色申告のままの人の理由:
- 「めんどくさそう」
- 「難しそう」
- 「そんなに変わらないでしょ?」
それにもかかわらず、年間数万円〜十数万円の節税効果を考えると、絶対に青色申告にすべきです。
注意すべき重要なポイント
それでは次に、特に注意すべき重要なポイントについて説明していきます。
1. 所得金額が控除額より少ない場合
これも意外と見落としがちなんですが、たとえば事業所得が30万円しかないのに65万円控除は受けられません。なぜかというと、控除額は所得金額が上限だからです。
例えば、事業所得が40万円の場合:
- 65万円控除を狙っていても、実際は40万円しか控除できない
- つまり課税所得は0円になる
このように、所得が少ない初年度などは、せっかく複式簿記で頑張っても控除額をフル活用できないことがあります。
2. 青色申告特別控除と基礎控除の混同
ここで注意したいのは、青色申告特別控除(最大65万円)と基礎控除(48万円)は別物だということです。両方受けられます。
3. 期限後申告のペナルティ
これ、めちゃくちゃ重要なんですが、実は55万円・65万円控除は期限内申告が必須条件なんです。
期限後申告になった場合:
- 55万円控除 → 10万円控除に格下げ
- 65万円控除 → 10万円控除に格下げ
要するに、せっかく複式簿記で頑張って帳簿つけても、申告が1日でも遅れると控除額が激減します。
具体例で計算すると: 事業所得300万円の場合
- 期限内申告(65万円控除):課税所得235万円
- 期限後申告(10万円控除):課税所得290万円
- 差額:55万円 → 税額差は約11万円
なんと1日遅れるだけで11万円の損失…これはヤバいですよね。
さらに期限後申告のダブルパンチ:
- 無申告加算税:原則として納付すべき税額の15%(50万円までの部分)
- 延滞税:年率最大14.6%(令和6年は8.8%)
仮に税額が20万円だった場合、無申告加算税だけで3万円追加。合計で14万円の損失になることも。したがって「うっかり忘れてた」では済まされない金額です。
こういった罰金について詳しく記載したこちらの記事もご参照ください
まとめ:私が思うコスパ最強の節税対策
結論として、青色申告特別控除は、私が見てきた中でもコスパ最強の節税対策だと思います。
とりわけ65万円控除は、(複式簿記というハードルがあるものの)e-Taxで申告すれば条件クリアできるので、やらない理由がありません。現在では、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを使えば、複式簿記も思ってるより簡単です(ただし、正しくできる保証はないので税理士にお願いするのが一番だと思いますが)。
確かに「めんどくさいなあ」って思う気持ちもわかります。しかしながら、年間10万円以上の節税効果を考えると、絶対やった方がいいです。
もし「自分でやるのは不安」という方がいれば、ぜひ私たち税理士に相談してみてください。初年度だけサポートしてもらって、翌年からは自分でやるという方法もありますよ。
よかったら国税庁のホームページも参考にしてみてくださいね