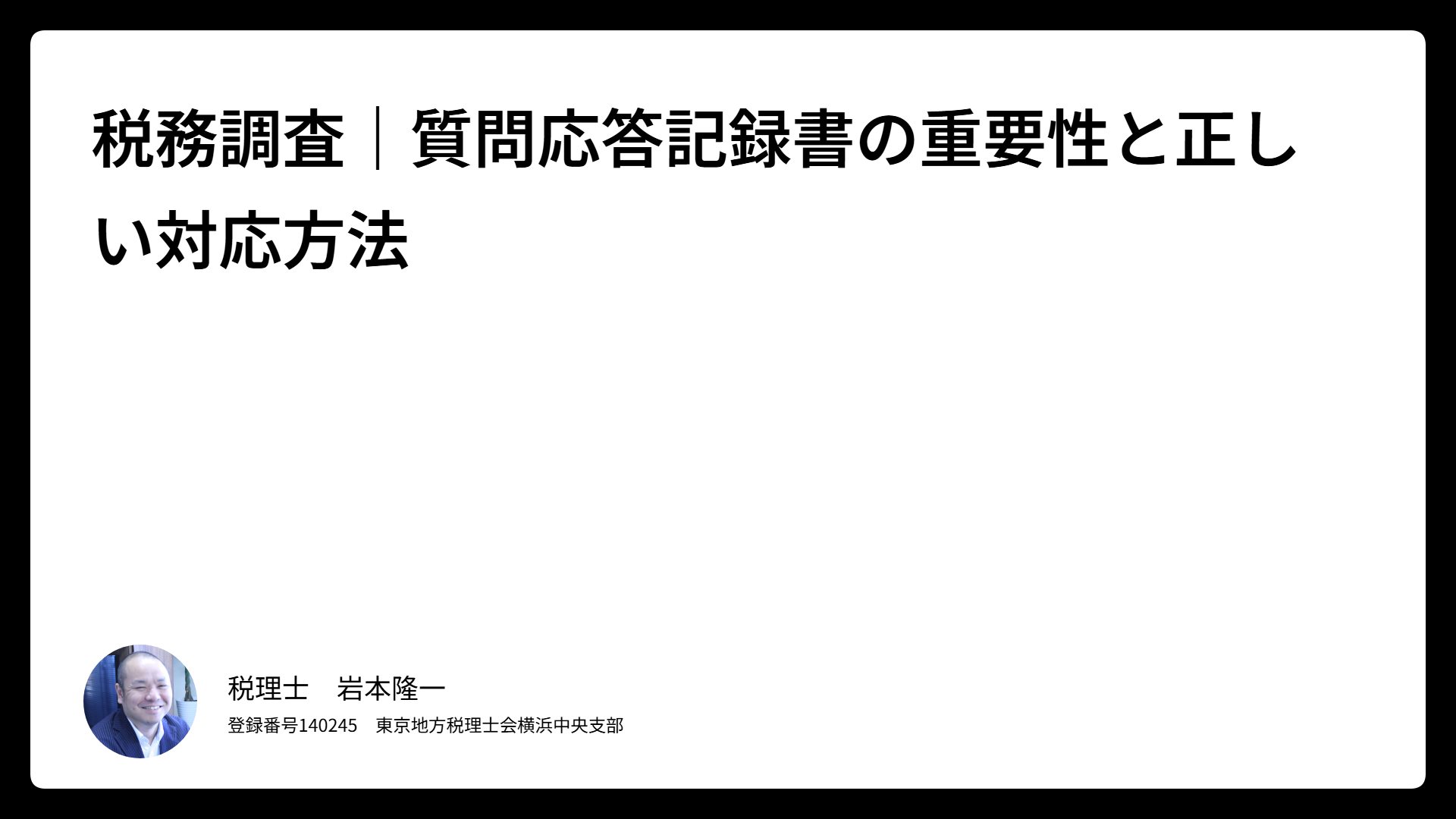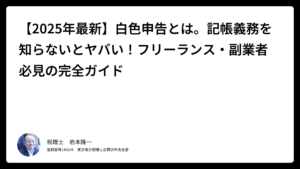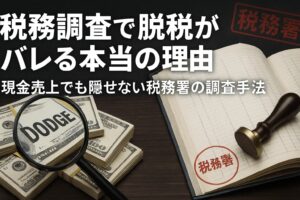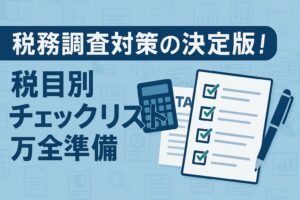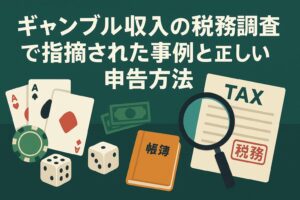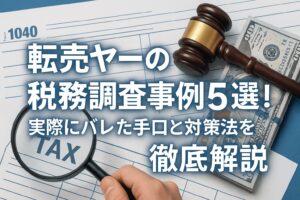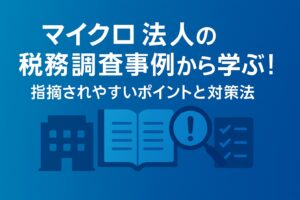今日は、税務調査で必ず出てくる「質問応答記録書」について話そうと思います。これ、実は超重要なんですが、意外と軽視されがちなんですよね。
僕も税理士として数々の税務調査に立ち会ってきましたが、質問応答記録書で失敗する人、めちゃくちゃ多いです。「とりあえず署名しちゃった」みたいな感じで。
でも、これって後で大きな問題になることがあるんです。だから今回は、質問応答記録書の重要性と、どう対応すべきかを詳しく解説していきます。
そもそも質問応答記録書って何?
質問応答記録書は、税務調査のときに調査官と納税者(あなた)の会話を記録する書類です。
正式名称は「調査手続に関する記録書」なんですが、実務では「質問応答記録書」とか「調査記録書」って呼ばれることが多いですね。
国税通則法第74条の11に基づいて作成される、れっきとした法定書類です。つまり、法律で決められた書類ってことです。
記録書に書かれる内容
- 調査日時と場所
- 出席者(調査官、納税者、税理士など)
- 調査官からの質問内容
- あなたの回答内容
- 提示された帳簿や資料
- その他の重要事項
要するに、「誰が、いつ、何を聞いて、何と答えたか」を全部記録するわけです。
なぜ質問応答記録書が重要なのか?
ここが一番大事なポイントです。質問応答記録書の重要性を理解していない人が多すぎる。
1. 法的証拠としての価値
質問応答記録書は、後で争いになったときの証拠になります。
例えば、税務署が「あなたはこう言いました」と主張してきたとき、記録書に書かれていることが事実として扱われるんです。
これ、めちゃくちゃ重要です。記録書に間違ったことが書かれていて、それに署名してしまったら、間違った内容が「事実」になってしまう可能性があります。
2. 後の処分に影響する
税務調査の結果、追徴税額が決まるときに、質問応答記録書の内容が参考にされます。
「故意に隠していたのか」「うっかりミスなのか」といった判断にも影響するので、記録書の内容次第で処分が重くなったり軽くなったりすることがあります。
3. 不服申立ての基礎資料
もし税務署の処分に納得できなくて不服申立てをする場合、質問応答記録書は重要な資料になります。
記録書に書かれた内容と実際の処分内容に矛盾があれば、それを根拠に争うことができるんです。
質問応答記録書への正しい対応方法
さて、ここからが実践編です。質問応答記録書にどう対応すべきか、具体的に説明しますね。
1. 内容を必ず確認する
これ、当たり前のようで、意外とできていない人が多いです。
調査官が記録書を作成して「確認してください」と言われたら、必ず一字一句チェックしてください。
チェックポイント:
- 日時や場所は正確か
- 質問内容は正しく記録されているか
- 自分の回答が正確に記載されているか
- 曖昧な表現や誤解を招く記述はないか
2. 間違いがあれば必ず修正を求める
「まあ、だいたい合ってるからいいか」は絶対ダメです。
少しでも事実と違うことが書かれていたら、遠慮なく修正を求めてください。調査官も人間なので、記録ミスは普通にあります。
修正を求めるときは、具体的に「この部分は○○ではなく××です」と伝えましょう。
3. 記録書に意見を付け加える
実は、質問応答記録書には自分の意見や補足説明を付け加えることができます。
例えば:
- 「調査官の質問の意図が不明確だった」
- 「十分な検討時間がなかった」
- 「資料を持参していなかったため、正確な回答ができなかった」
こういった事情があれば、遠慮なく記録に残してもらいましょう。
4. 署名・押印は慎重に
記録書の内容に納得してから署名・押印してください。
一度署名してしまうと、「記録書の内容に同意した」とみなされます。後から「あれは間違いだった」と言っても、なかなか通りません。
不安があれば、「内容を持ち帰って検討したい」と伝えることもできます。
5. 署名しない場合の理由を明確にする
もし記録書に署名しない場合は、調査官から理由を必ず聞かれます。その際は、合理的な説明をできるようにしておきましょう。
署名しない理由の例:
- 記録内容に事実と異なる部分があるため
- 質問の意図が不明確で、正確な回答ができていないため
- 必要な資料を確認してから回答したいため
- 税理士と相談してから判断したいため
曖昧な理由では調査官を納得させることができません。具体的で合理的な理由を準備しておくことが大切です。
よくある失敗パターン
税務調査の現場で見てきた、質問応答記録書でのよくある失敗を紹介します。
パターン1:曖昧な回答をしてしまう
「よく覚えていません」「たぶん○○だったと思います」みたいな曖昧な回答は避けましょう。
後で「記録書にこう書かれているじゃないですか」と言われたときに困ります。
パターン2:感情的になって余計なことを言う
税務調査って、どうしても感情的になりがちです。でも、余計な発言をすると、それも記録されちゃいます。
「税務署なんて信用できない」とか「前の税理士が悪い」とか、そういう発言は控えましょう。
パターン3:記録書を読まずに署名
これ、本当に多いです。調査官に「お疲れ様でした」と言われて、流れで署名してしまうパターン。
絶対にやめてください。記録書は必ず読んでから署名しましょう。
まとめ:質問応答記録書は慎重に対応しよう
質問応答記録書は、税務調査において極めて重要な書類です。
ポイントをまとめると:
- 内容は必ずしっかり確認する
- 間違いがあれば遠慮なく修正を求める
- 自分の意見や事情も記録に残してもらう
- 納得してから署名・押印する
「面倒くさいな」と思う気持ちはわかりますが、後で大きな問題になることを考えれば、ここでしっかり対応しておく方が絶対にいいです。
税務調査で質問応答記録書が出てきたら、今回の内容を思い出してくださいね。
もし税務調査でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。経験豊富な税理士として、しっかりサポートいたします。
税理士 岩本隆一
税務調査対応・企業税務のご相談承ります