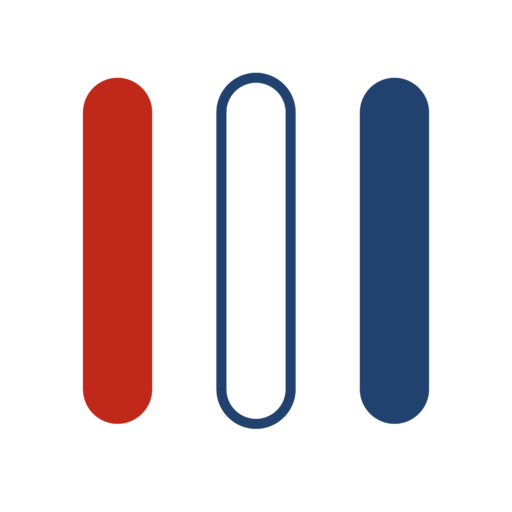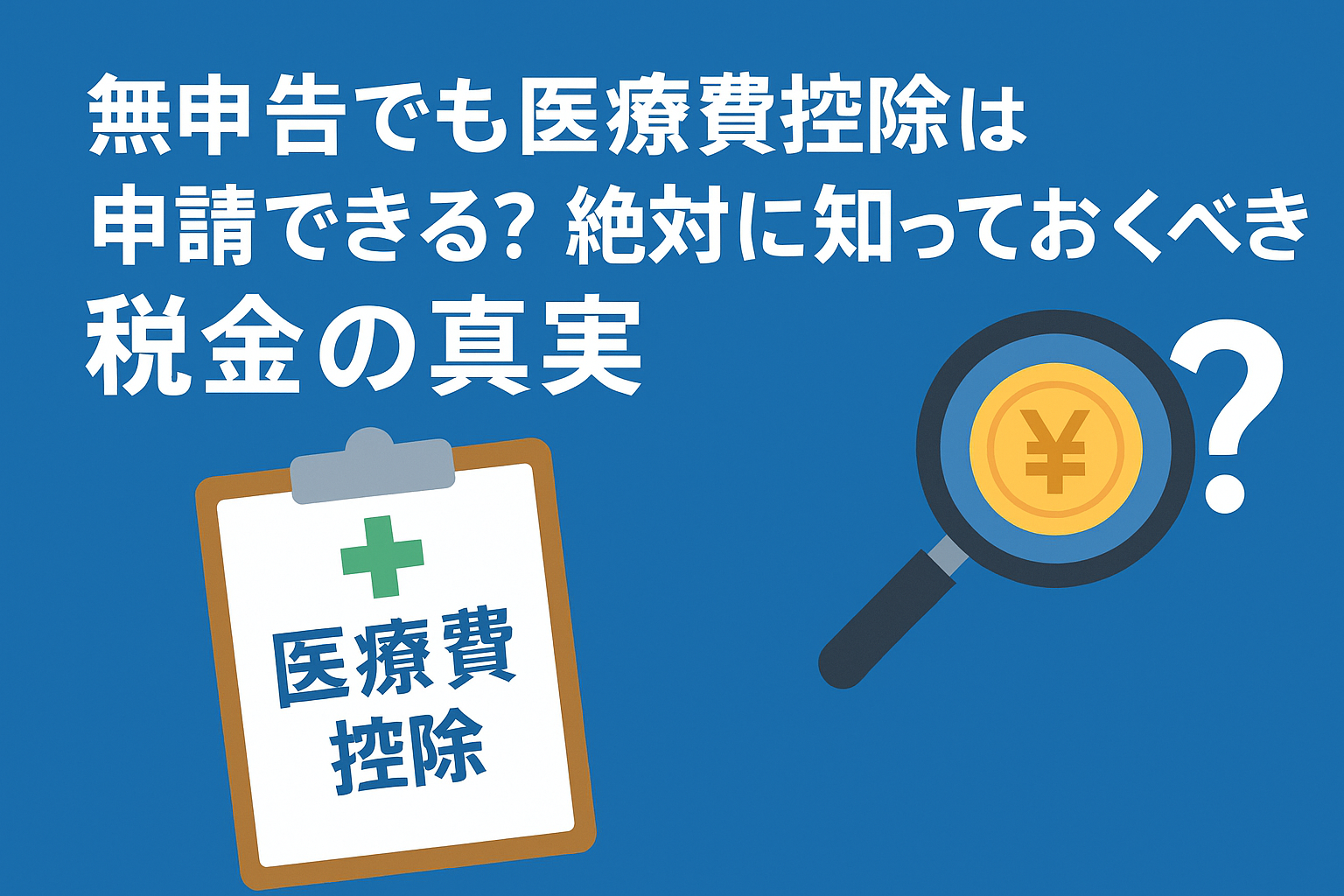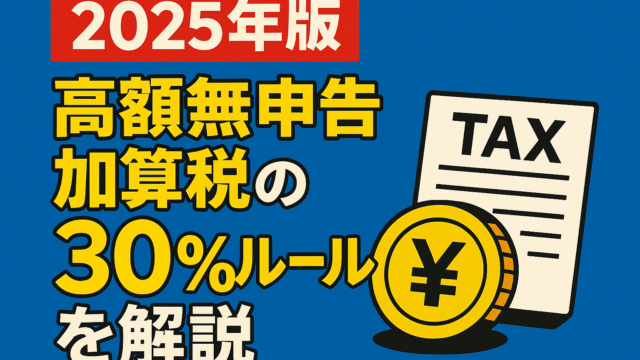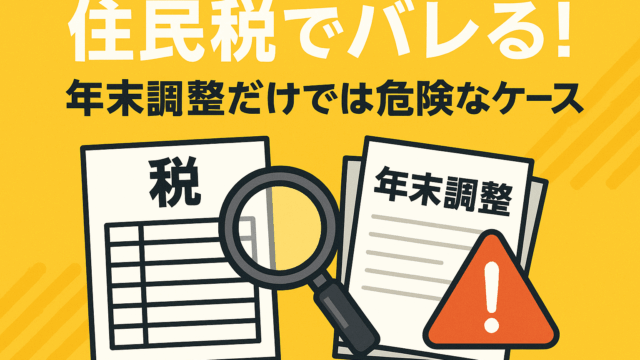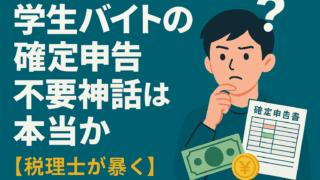みなさんこんにちは、税理士の岩本隆一です。無申告や税務調査を多く取り扱っている税理士事務所を営んでいます。(いつでもお問い合わせください!!)
「確定申告をしていなかったけど、去年すごく医療費かかったんだよね…」 「無申告だったら医療費控除って受けられないのかな…?」
こういう相談が超多いです。マジで多いです。
今日は「無申告でも医療費控除を申請できるのか?」という疑問にぶっちゃけベースでお答えします。これ、意外と知らない人が多いんですよね。
結論:無申告でも医療費控除は申請できる!むしろした方がいい!絶対に!
結論から言います。無申告でも医療費控除は申請できます!!
でも、無申告のまま医療費控除だけ申請するというのは不可能です。まず確定申告自体をする必要があるんです。でも、これはチャンスなんですよ!
無申告状態を解消しながら、同時に医療費控除も受けられるという、いわゆる「一石二鳥」というやつです。
無申告状態でも期限後申告で医療費控除が可能な理由
多くの方が誤解しているのが、「期限を過ぎたらもう申告できない」ということ。これは完全な間違いです。
確定申告には「期限内申告」と「期限後申告」があります。通常の申告期限(毎年2月16日~3月15日)を過ぎても、申告自体はいつでもできます。これを「期限後申告」と言います。(ただし、還付を受けられる“期限後(還付)申告”は翌年1月1日から5年間に限られます。)
医療費控除も期限後申告で請求することが可能です。ただし、還付を受けられる期間には制限があります。所得税の還付を受けることができるのは、原則としてその年の翌年1月1日から5年間です。つまり、5年前までの分なら医療費控除による還付を受けることが可能なんです。
無申告から期限後申告をする際の注意点
ただし、無申告状態から期限後申告をする際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
1. 加算税・延滞税が発生する可能性がある
期限後申告の場合、通常の税額に加えて「無申告加算税」や「延滞税」が課される可能性があります。ただし、還付申告(税金が戻ってくる申告)の場合は、原則として加算税は課されません。
でも注意!医療費控除を適用しても、最終的に納税額が生じる場合は加算税や延滞税が発生します。つまり、医療費控除だけでは税金がゼロにならない場合、ペナルティが発生するんです。
2. 自主的な申告はペナルティ軽減のチャンス
税務署から指摘される前に自主的に申告することには大きなメリットがあります。税務調査で指摘されてから申告する場合と比べて、無申告加算税の税率が大幅に軽減されます(通常15%~20%→5%)。
まじでこれ重要ですよ。先に自分から申告すると、ペナルティが1/3以下になります。なぜなら税務署は自主的に申告する姿勢を評価するからです。
3. 医療費の証明書類は必須!
医療費控除を申請するためには、医療費の領収書や明細書などの証明書類が必要です。最近は「医療費控除の明細書」の提出でもOKになりましたが、いずれにしても医療費を支払ったことを証明する書類は5年間保存する義務があります。
もし領収書を紛失してしまった場合でも、病院や薬局に問い合わせれば再発行してもらえるケースが多いです。あきらめずに問い合わせてみましょう!
無申告でも医療費控除を申請するメリット
無申告状態を解消しながら医療費控除を申請するメリットはめちゃくちゃ大きいです。具体的には以下のようなメリットがあります:
1. 税金の還付を受けられる可能性
医療費控除により、払い過ぎていた税金の還付を受けられる可能性があります。10万円以上(所得が200万円未満の場合は所得の5%以上)の医療費を支払った場合、その超えた分について控除を受けられるので、結構な額になることも多いです。
特に、給与所得者で源泉徴収されていた場合は、医療費控除による還付金が受け取れる可能性が高いです。
2. 無申告のリスクを解消できる
無申告状態は、いつ税務署からの調査が入るかわからない「時限爆弾」のような状態です。自主的に申告することで、このリスクを解消できます。
無申告が発覚した場合のリスクは想像以上に深刻です。ちなみに、虚偽無申告等の場合に罰則として最長10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されることがあるんです。まじでヤバいです。
3. クリーンな状態で新たなスタートが切れる
無申告だと住宅ローンや事業融資などの各種金融サービスを受けることが難しくなることがあります。特に将来的に法人設立や事業拡大を考えている場合は、クリーンな納税履歴であることで不利になることはないでしょう。
実際の申告手続きはどうすればいい?
では、具体的にどうやって無申告状態から医療費控除を含む確定申告をすればいいのでしょうか?
1. 必要書類の準備
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 医療費の領収書または「医療費控除の明細書」
- 各種控除証明書(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書など)
- マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
- 還付金の振込先口座情報
2. 確定申告書の作成
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、比較的簡単に申告書を作成できます。過去の分も作成可能です。所得や控除額を入力していくと、自動的に税額が計算されます。
3. 申告書の提出
作成した申告書は、税務署の窓口に持参するか、郵送で提出します。e-Taxでの提出も可能です。
提出期限を過ぎた申告書ても「期限後申告」と書く必要はありません。普通の申告と同じように提出しましょう!(逆に「期限後申告」と書いても問題はありません。)
よくある質問(FAQ)
Q: 無申告だと医療費控除の申請期限も過ぎてしまう?
A: いいえ。確定申告の期限(通常3月15日)を過ぎても、医療費控除を含めた期限後申告は可能です。ただし、還付を受けられるのはその年の翌年1月1日から5年間以内です。
Q: 数年分まとめて申告できる?
A: もちろん可能です!過去5年分までなら、まとめて申告することができます。ただし、年分ごとに別々の申告書を作成する必要があります。
Q: 無申告の期間が長いとペナルティは重くなる?
A: 基本的に、無申告期間の長さよりも「税額の大きさ」や「悪質性」によってペナルティの重さは変わります。ただ、延滞税は日数に応じて増えていくので、早めの対応が望ましいです。
まとめ:無申告を放置せず、医療費控除を活用しよう!
無申告でも医療費控除は申請できます!無申告でも医療費控除は申請できます!
大事なことなので二回言いました。むしろ、無申告状態を解消するきっかけとして医療費控除を活用する、という考え方がオススメです。
税金の問題は放置すればするほど大きくなります。特に無申告は、発覚した際のリスクが非常に大きい問題です。医療費控除という「得する制度」を利用しながら、無申告というリスクを解消できるなら、それは間違いなく賢明な選択と言えるでしょう。
期限後申告と医療費控除の手続きは、確かに面倒かもしれません。しかし、税金の還付を受けられる可能性や、将来的なリスクを回避できることを考えれば、十分にペイする「投資」だと言えます。
ぜひ、この機会に無申告状態を解消し、正しく医療費控除を受けてください。
わからないことがあれば、専門家である税理士に相談することも大切です。当事務所では、無申告案件や医療費控除に関するご相談を随時受け付けております。税金のことで悩んでいる方は、いつでもお気軽にご相談ください!!
税金の問題、一人で抱え込まないでくださいね。一緒に解決していきましょう!
当事務所ではいつでも相談をお請けいたしております。初回相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。過去の無申告問題も、医療費控除の申請方法も、なんでもご相談ください!!