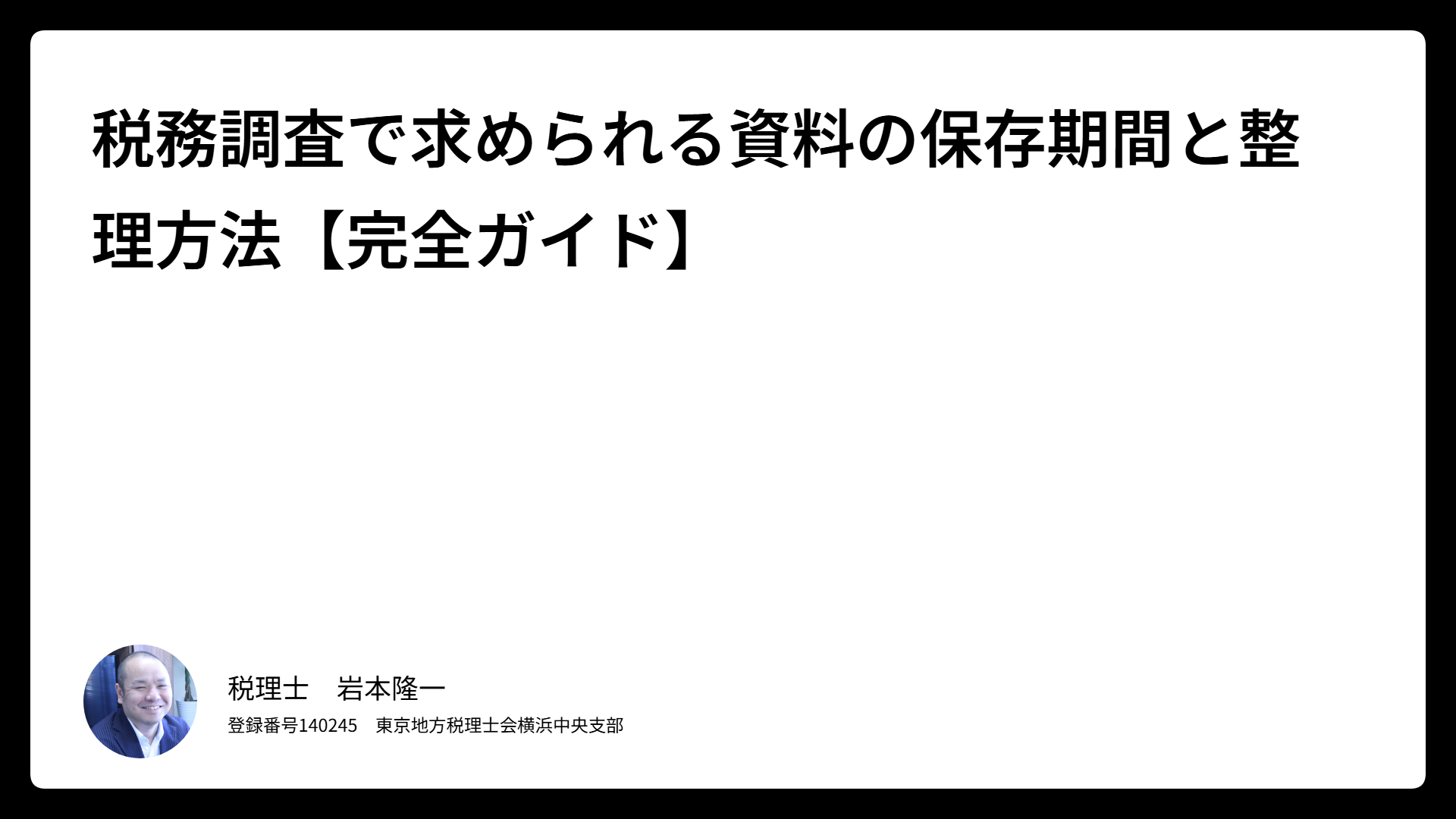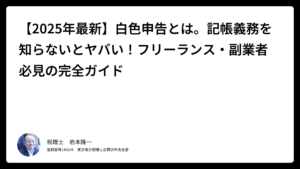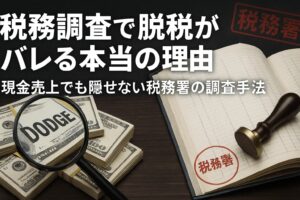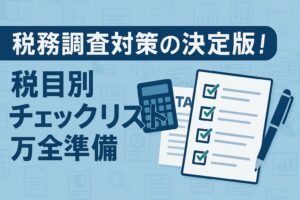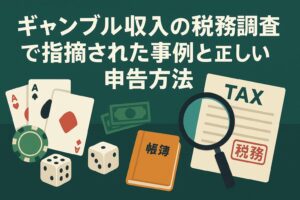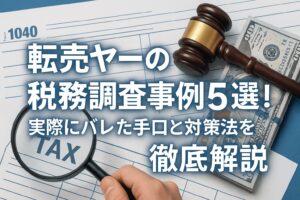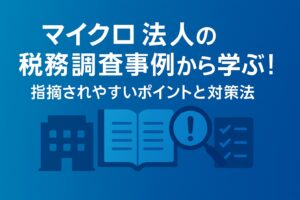今日は税務調査の話をしようと思うんですが、この話題って多くの人にとって「うわあ、嫌だなあ」って思うやつですよね。僕も最初は正直そうでした。
でも、実際に税務調査に立ち会うようになって気づいたことがあります。それは「準備さえしっかりしておけば、そんなに怖いものじゃない」ということです。
なぜ資料保存が重要なのか?実際の現場から
税務調査って、要するに税務署の人が「本当に正しく税金計算してる?」って確認しに来る作業なんですよね。で、その時に一番大事なのが「証拠」、つまり資料なんです。
僕が立ち会った調査で印象的だったケースがあります。ある個人事業主の方が「この経費、絶対に事業で使ったんです!」って主張されていたんですが、領収書がない。レシートもない。カードの明細はあるけど、何を買ったかわからない。
結果、どうなったかというと…まあ、察してください。
逆に、きちんと資料を整理していた法人の調査では、調査官の方も「よく整理されていますね」と感心していました。スムーズに進んで、結果的に何の問題もなく終了。この差、めちゃくちゃ大きいんです。
保存期間:「何年保存すればいいの?」問題を解決
税務調査における資料の保存期間、これがまた複雑なんですよね。でも、実務的に覚えるべきポイントは意外とシンプルです。
法人の場合
基本は7年間です。これは法人税法で決まっています。
- 帳簿
- 決算書類
- 領収書・請求書
- 契約書
- 給与関係書類
これらは全部7年。ただし、欠損金(赤字)がある場合は、その繰越期間に応じて9年~10年になることもあります。
ちょっと待って、会社法も忘れちゃダメ
実は、ここで注意が必要なのが会社法です。会社法では、以下の書類について10年間の保存義務があります:
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 計算書類(貸借対照表、損益計算書等)
- その附属明細書
つまり、法人の場合は「法人税法で7年、会社法で10年」という二重の規制があるんです。結果的に、安全を考えるなら10年保存が無難ということになります。
この辺り、結構見落としがちなポイントなので、覚えておいてください。
個人事業主の場合
個人の場合は少し複雑です:
- 青色申告者:帳簿や決算書類は7年、領収書等は5年
- 白色申告者:5年(ただし、300万円以下の所得なら収支内訳書等の一部書類のみ)
消費税関係
消費税関係の書類によって保存期間が違うって知ってました?
- 帳簿:7年間
- 請求書・領収書等:7年間
- 課税事業者選択届出書等の届出書:その届出書の効力が生じた日の属する課税期間の初日から7年間
ただし、免税事業者の場合は保存義務自体がありません。これは個人・法人問わず同じルールです。
実務的には「消費税関係は基本7年」と覚えておけばOKですが、届出書類については少し特殊なので、気をつけてください。
実際の現場でよく聞かれるのが「5年で捨てちゃったんですが…」というパターン。特に個人事業主の方で多いんですが、安全を考えるなら統一して7年にしておくのがおすすめです。
整理方法:「探せない」を防ぐテクニック
資料の整理って、みんな苦手ですよね。僕も昔は超苦手でした。でも、税務調査の現場を何度も経験して、「これなら誰でもできる」という方法を見つけました。
基本の「き」:年度別+項目別
まず大前提として、年度別に分けることから始めてください。
その上で、各年度の中を以下のように分類:
- 売上関係(請求書控え、入金確認書類)
- 仕入・経費関係(領収書、請求書)
- 給与関係(給与台帳、源泉徴収簿)
- 税務関係(申告書控え、納税証明書)
- その他(契約書、重要な書類)
デジタル化のススメ
最近は電子帳簿保存法の改正もあって、デジタル化が進んでいます。僕のおすすめは:
レシート・領収書
- スマホアプリでスキャン
- 月別フォルダに保存
- 元の紙も当面は保存
重要書類
- PDFで保存
- クラウドストレージにバックアップ
- 原本は別途保管
ただし、電子化には一定のルールがあるので、事前に確認が必要です。
「探せない問題」を解決する索引作り
これ、意外と盲点なんですが、索引を作ってください。
例えば:
2023年度 経費関係
├ 1月分(ファイル番号:2023-01)
├ 2月分(ファイル番号:2023-02)
└ ...
こんな感じで、どこに何があるかをリスト化しておく。税務調査の時に「○月の△△の領収書を見せてください」と言われても、すぐに出せます。
税務調査でよく求められる資料一覧
実際の調査現場でよく求められる資料をリストアップしてみます:
必ず求められるもの
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 現金出納帳
- 売掛帳・買掛帳
- 決算書類一式
業種によって求められるもの(代表的な例)
- 小売業:売上明細、仕入明細、在庫管理表、人件費関係
- 建設業:工事台帳、外注費明細
- サービス業:売上明細、人件費関係
個人的な支出と事業支出の区別が重要なもの
- 車両関係費(ガソリン代、駐車場代)
- 通信費(携帯電話、インターネット)
- 接待交際費
注意すべきポイント:現場で見た「あるある」失敗
その1:現金取引の記録が曖昧
「現金で払ったから記録がない」というパターン。これ、税務調査で一番厳しく見られます。現金取引こそ、しっかりとした記録が必要。
その2:個人用途と事業用途が混在
特に個人事業主の方に多いんですが、プライベートの支出と事業の支出がごちゃ混ぜになってしまうケース。按分計算の根拠を明確にしておくことが大切です。
その3:「だいたい」で処理している
「だいたい7:3で按分している」みたいな、根拠が曖昧な処理。調査官は必ず「なぜその比率なんですか?」と聞きます。
まとめ:準備が全て
税務調査って、結局のところ「準備が全て」なんです。
日頃からきちんと資料を整理して、保存期間を守って、必要な時にすぐ出せるようにしておく。これができていれば、税務調査は怖いものじゃありません。
逆に、準備ができていないと…まあ、大変なことになります。
最後に、もし「自分だけでは不安」「専門家に相談したい」という方は、遠慮なくご連絡ください。税務調査の立ち会いから、日頃の帳簿整理のアドバイスまで、しっかりサポートさせていただきます。
みなさんの事業が、税務面でも安心して運営できるよう、お手伝いできればと思っています。