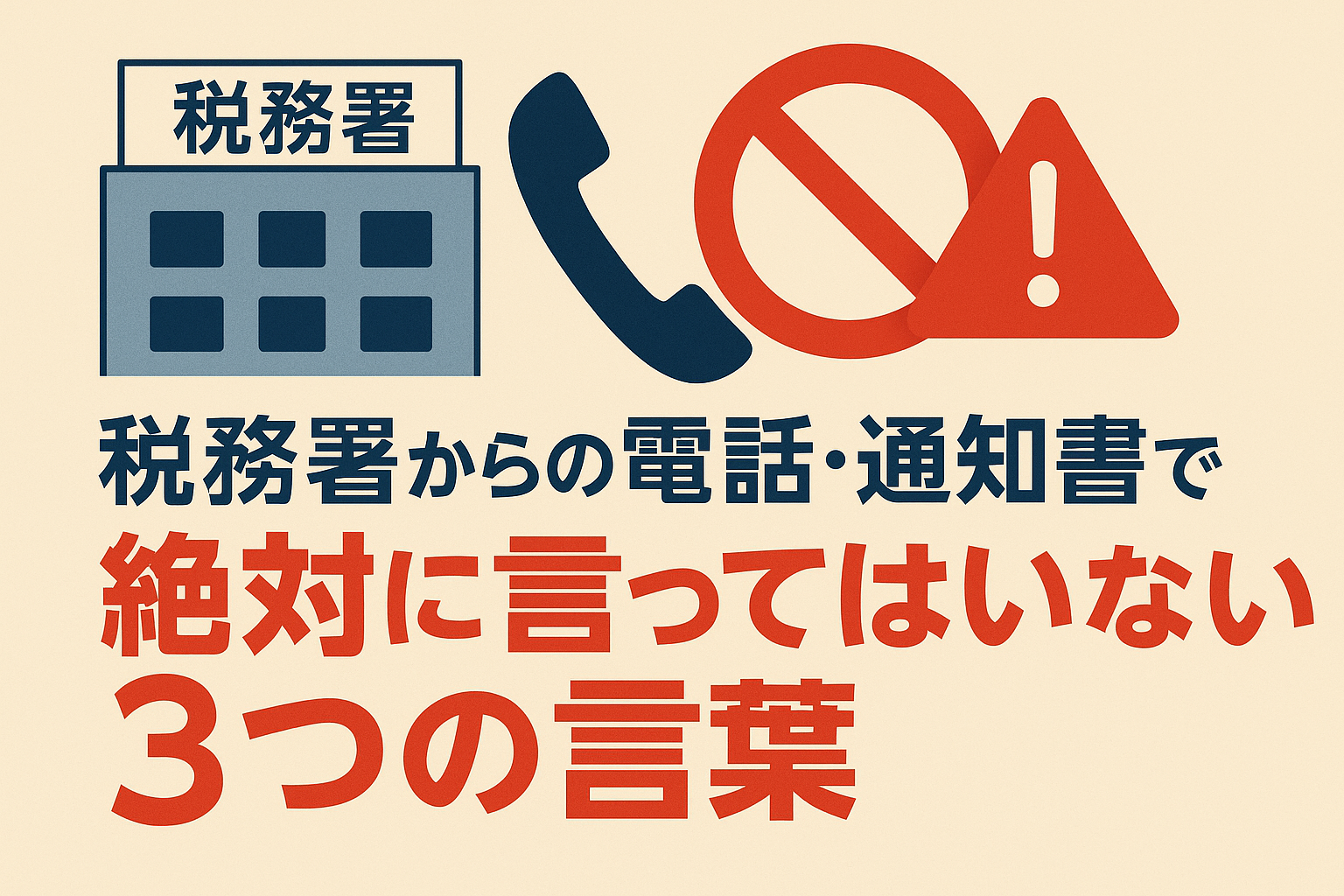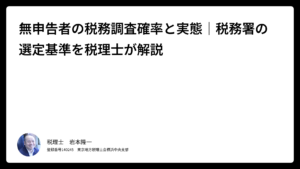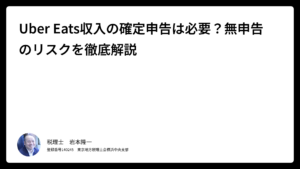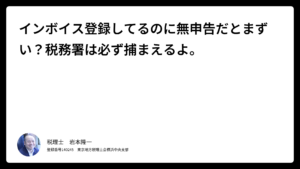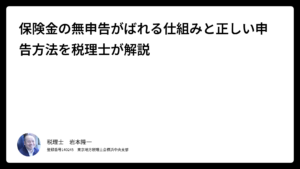「税務署から電話がきた…」
このフレーズを聞いただけで、背筋が凍るような感覚を覚えた経験はありませんか?あるいは、なにげなく郵便ポストを開けたら、差出人が「税務署」の通知書が…なんてこともあるでしょう。
いずれにせよ「ヤバい…何かやらかしたかな」という心理状態になることは間違いありません笑
でも実は、この「税務署からの連絡」という局面、対応次第で全然結果が変わってくるんですよね。下手に出るのもダメだし、強気に出るのも危険。「何を言うか・言わないか」が超重要なタイミングなんです。
私の事務所には、税務署とのやり取りで自爆してしまったケースの相談が山ほど寄せられます。よくあるのが「焦って余計なことを言ってしまった」「知らなくていいことまで正直に話した」というパターン。
正直、ほとんどの人は税務署と話す訓練を受けていません。それは当然です。だからこそ、いざという時の「NGワード」を知っておくことが、あなたの財産と心の平和を守る鍵になるんです。
今回は、税務署からの電話や通知を受けた際に絶対に言ってはいけない3つのフレーズと、その代わりに何を言うべきかをお伝えします。さらに「期限後申告」のペナルティ計算方法や、自主申告のメリットも解説します。これさえ読めば、税務署からの連絡にも冷静に対応できるようになりますよ。
1. そもそも「期限後申告」って何?税務署からの連絡の一部はコレ
「確定申告、忘れてた…」 「期限、とっくに過ぎてた…」
こんな経験、ありませんか?(若い頃の私だけじゃないはず…🙄)
確定申告には期限があって、所得税なら毎年2月16日〜3月15日まで。この期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」と呼びます。実は税務署からの連絡の一部には、この期限後申告に関するものがあります。
期限後申告の手続き:意外と簡単
期限後申告は難しそうに聞こえますが、やることは普通の確定申告とほぼ同じです。特別な書類も不要。
ただ「遅れました、すみません🙇♂️」という気持ちで普通に申告書を出すだけ。
- 申告方法: 通常の確定申告書(第一表、第二表など)に必要な情報を記入して提出します。過去の申告内容を修正する場合は、納税額を少なく申告していた場合は「修正申告」、多く申告していた(還付が少ない)場合は「更正の請求」という手続きになります。
- 提出場所: 納税地を管轄する税務署に提出します。郵送や時間外収受箱への投函、あるいはe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子申告も可能です。e-Taxを利用すれば、税務署の閉庁後でも提出できます。
- 必要書類: 基本的に通常の確定申告と同じ書類が必要です。確定申告書、青色申告決算書(青色申告の場合)または収支内訳書(白色申告の場合)、各種控除証明書(保険料控除、医療費控除など)、源泉徴収票、マイナンバー関連書類、収入や経費の根拠となる領収書や帳簿類などを用意します。
- 過去の申告: 確定申告は過去分に遡って行うことも可能です。修正申告や更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内、還付申告も該当年の翌年1月1日から5年間可能です。
期限に遅れたことに気づいたら、一日でも早く申告することが重要です。放置すればするほど、次に説明するペナルティが重くなる可能性があります。
2. 申告が遅れると発生する「3つの痛い罰」:知らないと損します
よく「申告が遅れてもペナルティなんてたいしたことないでしょ?」と思っている人がいますが、これが大間違い。
ペナルティは思った以上に痛いんです。私の事務所に相談に来るクライアントの中には、ペナルティだけで数百万円になってしまったケースもあります。あなたの大切なお金が国庫に吸い込まれていくイメージですね…😱
では具体的にどんなペナルティがあるのか、順番に見ていきましょう。
無申告加算税:自主申告なら激減する謎の仕組み
期限内に申告しなかったことに対するペナルティです。原則として、納付すべき税額に対して以下の税率が課されます。
- 50万円までの部分: 15%
- 50万円超 300万円以下の部分: 20%
- 300万円超の部分: 30%
ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告した場合、税率は5%に軽減されます。これは非常に大きな軽減措置であり、自主的な行動がいかに重要かを示しています。さらに、税務調査の事前通知を受けた後、調査が始まる前に自主的に申告した場合でも、10%(50万円超の部分は15%、場合により300万円超は25%)に軽減されることがあります。
なお、以下の要件をすべて満たす場合は、無申告加算税は課されません。
- 法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告をしていること。
- 期限後申告にかかる税額を法定納期限(原則として本来の申告期限)までに全額納付していること。
- 過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがないこと(一定の場合)。
また、計算された無申告加算税額が5,000円未満の場合も徴収されません。
延滞税
法定納期限(原則3月15日)までに税金を納付しなかった場合に、利息に相当するものとして課される税金です。納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて計算されます。税率は年によって変動しますが、納期限の翌日から2ヶ月を経過するかどうかで異なります。
- 納期限の翌日から2ヶ月以内: 年7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合(例: 令和4年~令和7年は年2.4%)。
- 納期限の翌日から2ヶ月経過後: 年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(例: 令和4年~令和7年は年8.7%)。
延滞税は日割りで計算されるため、納付が遅れれば遅れるほど金額が増えていきます。1日でも早く納税することが負担軽減につながります。なお、納付すべき本税額が1万円未満の場合は延滞税はかからず、計算された延滞税額が1,000円未満の場合も徴収されません。
青色申告特別控除の減額
青色申告を行っている個人事業主などが受けられる青色申告特別控除(最大65万円または55万円)は、期限内に申告することが要件の一つです。期限後申告になると、たとえ他の要件を満たしていても、控除額は10万円に減額されてしまいます。これにより、所得税や住民税の負担が大幅に増える可能性があります。
重加算税
これは最も重いペナルティで、意図的に所得を隠したり(隠蔽)、事実を偽って申告したり(仮装)した場合に課されます。単なる計算ミスや申告忘れではなく、悪質な不正行為に対するものです。
- 過少申告(修正申告)の場合: 追加で納める税額の35%。
- 無申告の場合: 納付すべき税額の40%。
過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合、さらに10%が加重されることもあります。重加算税が課されると、税務調査の対象期間が通常より長くなる(最大7年)可能性もあります。
これらのペナルティを避ける、あるいは最小限に抑えるためには、期限を守ることが最も重要ですが、万が一遅れてしまった場合は、速やかに自主的に正しい申告・納税を行うことが最善策となります。
3. 税務署からの連絡:電話と通知への心構え
税務署から連絡が来る理由は様々です。確定申告書の内容確認(いわゆる「お尋ね」)、添付書類の不足、納税の確認・催促、そして税務調査の日程調整や事前通知などが考えられます。取引先の調査(反面調査)に関連して連絡が来ることもあります。
連絡手段としては、電話や封書、ハガキなどが用いられます。突然の連絡に驚くかもしれませんが、まずは落ち着いて対応することが大切です。
- 相手の確認: 最初に、相手の所属(税務署名・部署名)と氏名を確認しましょう。
- 用件の確認: 何のための連絡なのか、簡潔に用件を確認します。
- メモを取る: 相手の情報、連絡日時、用件、話した内容などを記録しておくと、後で確認したり税理士に相談したりする際に役立ちます。
- 詐欺に注意: 税務署職員を名乗る詐欺も存在します。特に「還付金があるからATMへ」「税金の納付のために口座番号を教えてほしい」といった電話は詐欺の可能性が高いです。税務署が電話で口座情報を聞いたり、ATM操作を指示したり、アンケート調査をしたりすることはありません。不審に思ったら、即答せず、税務署の代表電話番号にかけ直して確認しましょう。
- 無視はしない: 連絡を無視したり放置したりするのは最悪の対応です。税務署の不信感を高め、状況を悪化させる可能性があります。留守番電話にメッセージがあれば必ず折り返し、書面が届けば内容を確認し、必要であれば対応しましょう。
4. 税務署からの電話・通知で絶対に言ってはいけない「禁断の3フレーズ」
さて本題です。税務署とのやり取りで、うっかり言ってしまって後悔する言葉があります。以下の3つのフレーズを発した瞬間、あなたの立場は一気に不利になります。税理士としての経験から言うと、この3つの言葉が「自爆の原因ランキング」のトップ3です。
禁断フレーズ1:「具体的に何を調べているんですか?」「何が問題なんですか?」
税務署から「調査させていただきたいのですが」と連絡があったとき、ほとんどの人が思わず「何か問題があったんですか?」と聞いてしまいます。この質問、直感的には自然なのですが、税務戦略的には大失敗なんです。
なぜ地雷なのか?
- 自分の首を絞める情報提供: 「もしかして〇〇のことですか?」「△△の経費のことでしょうか?」と具体的に質問すると、調査官の「おや?」スイッチが入ります。本来注目されていなかったポイントに、自分から「ここ怪しいですよ!」と言っているようなものです。
- 自主申告のチャンス喪失: ここ重要です。税務署が具体的な指摘をする前に自主的に修正申告すれば、ペナルティが激減するか、場合によってはゼロになります。でも「何が問題か」を先に聞いてしまうと、「自主的」とはみなされにくくなります。5%と15〜30%、どっちがいいか考えれば明らかですよね。
- 時間の無駄: この段階での電話は多くの場合、単なる日程調整です。内容を聞き出そうとしても教えてくれません。貴重な準備時間を浪費するだけです。
代わりに何を言うべきか
- 「ご連絡ありがとうございます。日程調整のためでしょうか?」と相手の用件だけを確認。
- 「内容を確認して、税理士と相談の上、改めてご連絡します」と一旦切るのがベスト。
- 決して自分から「心当たり」を話さない。これ鉄則です。
禁断フレーズ2:「はい、明日(すぐ)で大丈夫です」
税務署から「調査にお伺いしたいのですが」と連絡があったとき、多くの人が「早く終わらせたい」という一心で、「明日でも大丈夫です!」と即答してしまいます。
これ、めちゃくちゃ危険です。
なぜ地雷なのか?
- 準備時間ゼロ=丸腰で戦場へ: 税務調査では通常3〜7年分の帳簿や領収書、通帳などを確認します。これら全部を急に整理できますか?「あの領収書どこだっけ…」と調査官の前で冷や汗をかくことになります。私の経験では、準備不足の調査ほど悲惨な結果になりがちです😱
- 自分で自分を追い込む: 申告内容に誤りがあった場合、調査前に修正申告すれば過少申告加算税がゼロになったり、無申告加算税が大幅減額されたりします。でも即日調査を受けると、この「自主修正」のチャンスを自ら放棄することに。
- 頼れる味方なし: 税務調査には税理士の立ち会いが重要です。「明日OK」と言ってしまうと、税理士のスケジュール調整も難しく、一人で調査官と向き合うことに。これは素人がプロボクサーと素手で戦うようなものです。
代わりに何を言うべきか
- 「日程については確認の上、改めてこちらからご連絡させていただけますか?」と即答を避ける。
- 税理士に相談した上で、最低でも2週間〜1ヶ月後の日程を提案するのがベスト。
- その間に必要書類を整理し、場合によっては修正申告も検討。
禁断フレーズ3:「たぶん大丈夫だと思います」「覚えてないです」「(ウソの)ありません」
これが最も危険な言葉かもしれません。税務署からの質問に対して曖昧に答えたり、適当に「大丈夫です」と言ったり、思い出せないからと「覚えていない」と答えたり、あるいは最悪のケースでは「そんな取引はありません」とウソをついたり…。
こういった対応は、税務調査の世界では「一発レッドカード」です。
なぜ地雷なのか?
- 信頼ゼロ=全面戦争へ: 曖昧な回答や「覚えていない」の連発は、調査官の不信感を爆上げします。特に意図的な虚偽答弁や隠蔽が発覚すると、最悪のペナルティである重加算税(35%〜40%!)が課される確率が激増。調査官は嘘を見抜くプロフェッショナルです。私の事務所でも「軽い気持ちで嘘をついたら重加算税を取られた」という相談が後を絶ちません。
- 調査が無限に長引く: 曖昧・不明確な回答をすると、調査官は「この人、何か隠してるな」と警戒し、より細かく、より広範囲の調査を始めます。通常1日で終わる調査が、1週間、場合によっては複数回に…😨
- 法的リスク: 税務調査は「任意」と言われますが、納税者には誠実に回答する法的義務があります。虚偽答弁は単なる「ペナルティ増額」だけでなく、最悪の場合は税務署告発という道も…。
代わりに何を言うべきか
- 正直に答える: 事実を伝える。誤りがあれば認める。これが鉄則です。
- 「わかりません」ではなく「確認します」: すぐに答えられない場合は「調べて後日回答します」と時間をもらう。
- 税理士を盾に: 複雑な質問には「税理士に確認して回答します」と専門家に振る。
- 推測で答えない: 「たぶん…」「思います…」は絶対NGワード。事実と記録に基づいてのみ回答する。
ちなみに私の経験上、「ごめんなさい、それは間違っていました」と正直に認めるケースの方が、ごまかし続けるケースよりもはるかに結果が良いです。税務署員も人間、誠実さには応えてくれます。
5. 状況をコントロールする:自主的な行動と専門家の活用
期限後申告になってしまった場合や、税務署から連絡があった場合でも、受け身にならず、主体的に行動することで状況を改善できる可能性があります。
自主的な行動の力
繰り返しになりますが、期限後申告に気づいたら、税務署から連絡が来る前に、一日でも早く自主的に申告・納税することが最も重要です。
- 無申告加算税の軽減: 自主申告により、無申告加算税の税率が15%∼30%から5%へと大幅に軽減されます。
- 延滞税の抑制: 納付までの日数が短くなるため、延滞税の総額を抑えることができます。
- 信頼性の維持: 自ら誤りを是正する姿勢は、税務署に対して誠意を示すことになり、無用な疑念を招くリスクを減らせます。
この「自主的に行動する」という原則は、ペナルティの軽減だけでなく、税務署との円滑なコミュニケーションを図る上でも、極めて有効な戦略と言えます。
修正申告の戦略的活用
期限内に申告したものの、後日、所得の申告漏れや経費の過大計上などの誤りに気づいた場合は、「修正申告」を行います。税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告を行えば、原則として「過少申告加算税」(通常10%または15%)は課されません。ただし、追加で納める税金に対する延滞税は、本来の納期限の翌日から発生します。
たとえ税務調査の通知を受けた後であっても、調査開始前に修正申告を行うことは、調査で指摘されるよりも心証が良い場合があり、悪質性(重加算税の適用判断)の観点からも有利に働く可能性があります。
税理士(税務の専門家)への相談
以下のような場合は、税理士への相談を強く推奨します。
- 複雑な申告: 事業所得がある、不動産所得がある、複数年分の申告が必要など、内容が複雑な場合。
- 税務調査の通知: 税務調査の連絡があった場合は、速やかに税理士に相談しましょう。調査の準備、対応方法のアドバイス、調査当日の立ち会いなど、専門的なサポートが受けられます。税務調査に精通した税理士を選ぶことが重要です。
- 手続きや対応への不安: 期限後申告や修正申告の手続き、税務署からの問い合わせへの回答方法などに不安がある場合。
- 納税資金の相談: 税金やペナルティの支払いが困難な場合、納税の猶予制度の申請や分割納付の相談など、税理士が代理で行えることもあります。
税理士は、単なる計算代行者ではなく、複雑な税法や税務署との対応において、納税者の権利を守り、リスクを最小化するための重要なパートナー(盾)となり得ます。
利用できる可能性のある救済措置
納税が困難な状況にある場合、以下のような制度を利用できる可能性があります。
- 納税の猶予制度: 災害、病気、事業の著しい損失など、特定の理由で一時的に納税が困難な場合に、申請により原則1年以内の分割納付や納税の猶予が認められることがあります。猶予期間中は延滞税が軽減または免除される場合があります。
- 災害による特例: 大規模な自然災害などの場合、申告・納付期限の延長や納税の猶予などの特別な措置が設けられることがあります。国税庁のウェブサイトなどで最新情報を確認してください。
これらの制度を利用するには、申請と状況を証明する書類が必要です。該当する可能性がある場合は、税務署や税理士に相談してみましょう。
まとめ:「税務署との対話」で生き残るための3原則
いかがでしたか?税務署とのコミュニケーションは、まさに「言葉のマインフィールド(地雷原)」です。一歩間違えると大爆発…。
今回お伝えした「絶対NGな3フレーズ」をおさらいしましょう:
- 「何を調べてるんですか?」「何が問題なんですか?」:自分から怪しいポイントを教えるようなもの。調査官にヒントを与えず、まずは税理士に相談を。
- 「はい、明日でも大丈夫です!」:準備なし・対策なしで調査を受けるという危険行為。少なくとも2週間〜1ヶ月の猶予期間をもらって準備を。
- 「たぶん…」「覚えてない…」「(ウソの)ありません」:曖昧・不正確な回答や虚偽は最悪の結果を招く。事実に基づき、正直に、わからないことは「確認します」と。
そして、もし確定申告を忘れていたことに気づいたら、税務署から連絡が来る前に、一刻も早く自主申告してください。ペナルティが劇的に減額されますよ(15〜30%→5%へ!)。
私がこの記事で一番伝えたいことは、「あわてず、パニックにならず、専門家に相談する」ということ。
「税務のプロ」である税務署との対話は、同じく「税務のプロ」である税理士のサポートがあれば、ずっと対等に戦えます。野球で例えると、プロ投手と対決するなら、プロバッターのアドバイスを受けた方が良いでしょう?同じことです。
当事務所では無申告や税務調査対応の相談を数多く受けています。「こんなこと聞いていいのかな…」と思わず、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの大切なお金と心の平和を守るお手伝いをさせていただきます。
では、また次回のブログでお会いしましょう!