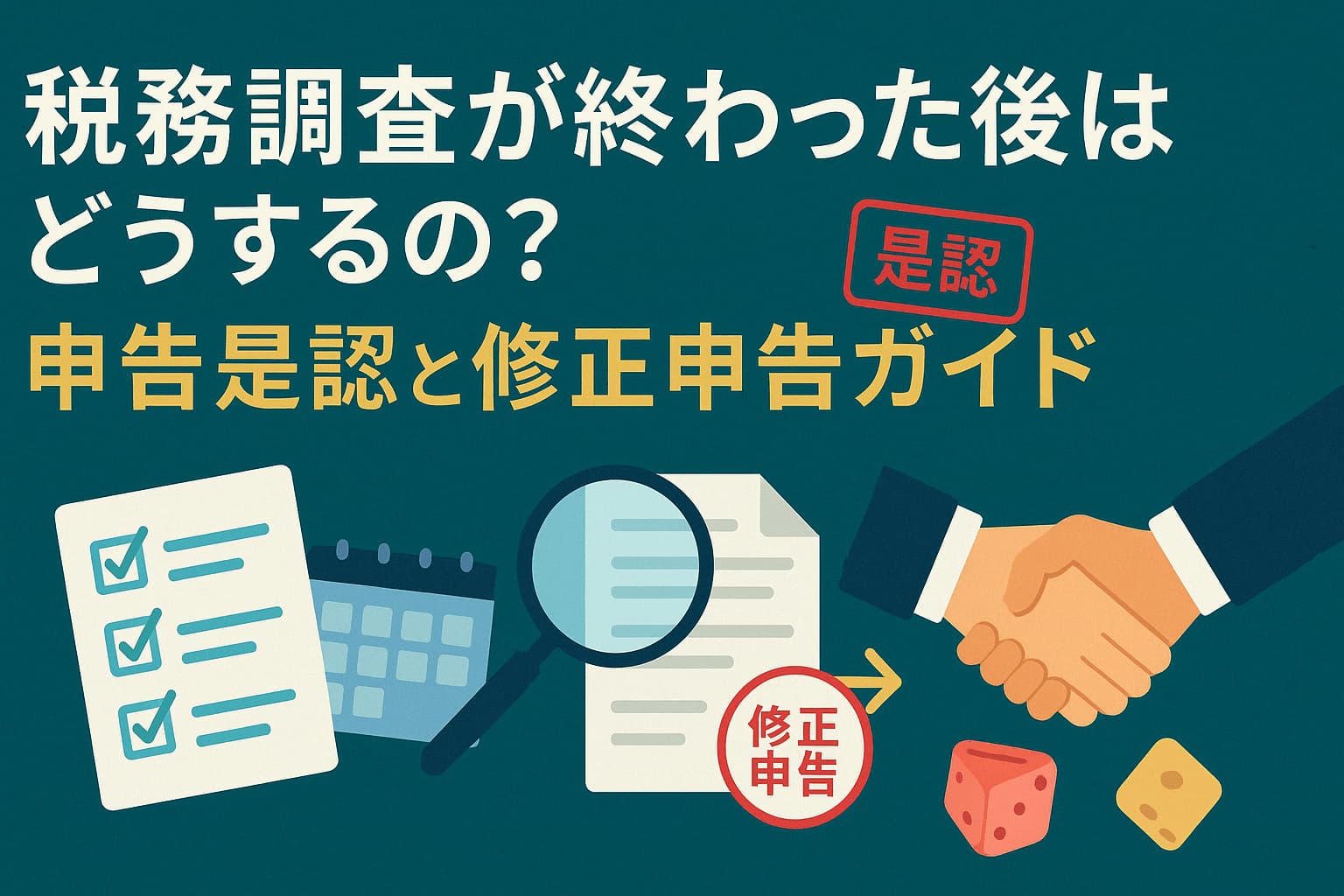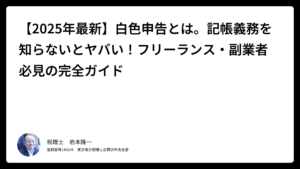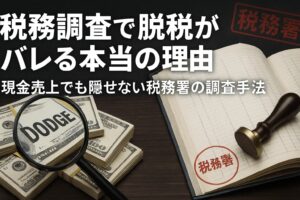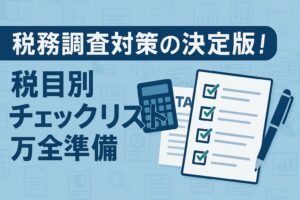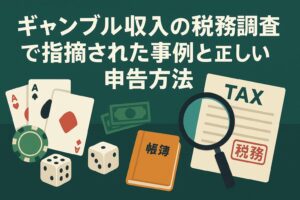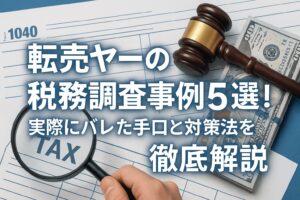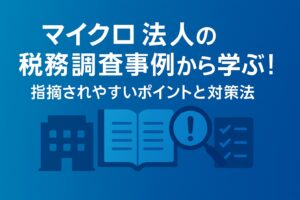税務調査が終わった後はどうするの?申告是認と修正申告ガイド
税理士の岩本隆一です。税務調査のご依頼募集中です。
どうも、皆さん。今日は「税務調査が終わったら何が起こるの?」という、めちゃくちゃ気になるけど意外と知られていない話をしようと思います。
税務調査って、「終わったー!」って思った瞬間から、実は新しいフェーズが始まるんですよね。これ、知らない人が多すぎて、いつも「えっ、まだ続くの?」って顔をされます。
税務調査の結末は2パターンしかない
まず基本的な話から。税務調査が終わると、結果は必ず以下の2つのどちらかになります。
①申告是認(しんこくぜにん) 「あなたの申告、完璧でした!」ということ。これが理想ですね。
②修正申告 「ちょっと間違いがありましたので、直してください」ということ。
で、実際のところ、①の申告是認になるケースって、正直そんなに多くないんですよ。なぜかというと、税務署の人たちも「何も見つからなかった」では、上司に怒られちゃうから。少しでも「あ、これちょっと違うかも」というポイントを見つけて帰りたがるのが人情というものです。
申告是認になった場合
申告是認の場合は、本当にシンプル。「お疲れさまでした」で終了です。
税務署から「調査結果についてのお知らせ」みたいな書類が送られてきて、「今回の調査において、申告内容に誤りは認められませんでした」的なことが書いてあります。
これが来たら、もう安心して大丈夫。少なくとも同じ年度については、もう一度税務調査が来ることはほぼありません。
ただし、油断は禁物。申告是認だからといって、今後の申告がテキトーでいいわけではないですからね。
修正申告になった場合(ここが重要)
問題は修正申告になった場合です。これが今回の記事のメインディッシュ。
修正申告の流れ
- 調査結果の説明 税務調査官から「○○の処理が間違っていました」という説明を受けます。
- 修正申告書の作成 間違いを直した申告書を作り直します。
- 追加税額の計算 本税(足りなかった分の税金)+加算税+延滞税を計算します。
- 修正申告書の提出 税務署に提出して、追加税額を納付します。
修正申告で発生する3つの税金
修正申告になると、元の税金以外に以下の税金がかかります。
①本税 これは単純に「足りなかった税金」です。当然払わなければいけません。
②過少申告加算税 「申告をサボった罰金」みたいなもの。通常は追加税額の10%(50万円超の部分は15%)です。 ただし、税務調査が入る前に自分で修正申告していれば、これはかかりません。
③延滞税 「税金の支払いが遅れた利息」です。年利は時期によって変わりますが、だいたい年2.4%〜8.7%くらい。
この3つが合わさると、けっこうな金額になります。だから「バレなければいいや」という考えは、本当におすすめしません。
修正申告を回避する方法はあるのか?
よく聞かれるのが「修正申告にならない方法はないの?」という質問。
実は、完全に回避することは難しいんですが、以下のような場合は修正申告を行わない手続きとなります。
更正の請求という逆パターン
もし税務調査の結果、「実は税金を払いすぎていた」ことが判明した場合、「更正の請求」という手続きで税金を返してもらえます。
これは修正申告の逆で、納税者にとっては嬉しいパターンですね。
争う場合
税務署の指摘に納得がいかない場合は、争うこともできます。
- 異議申立て
- 審査請求
- 訟訴
ただし、これらは時間もお金もかかるので、よほど確信がある場合以外はおすすめしません。
修正申告のタイミングが超重要
修正申告には「いつやるか」がめちゃくちゃ重要です。
調査通知前 自分で間違いに気づいて修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。
調査通知後〜調査終了後 通常の過少申告加算税がフルでかかります。
つまり、早ければ早いほどお得ということです。
まとめ:税務調査後の心構え
税務調査が終わった後の流れをまとめると:
- 申告是認なら素直に喜ぶ
- 修正申告なら速やかに対応する
- 追加税額の支払いは期限を守る
- 今後の申告はより注意深く行う
一番大切なのは「税務調査は恐れるものではなく、学ぶ機会」だと考えることです。
修正申告になったとしても、それで会社が潰れるわけではありません。むしろ、正しい処理方法を学べる貴重な機会だと前向きに捉えましょう。
それに、一度税務調査を経験すると、次回からの申告精度は格段に上がります。これは間違いありません。
というわけで、税務調査後の流れについて解説しました。不安になることもあるかもしれませんが、正しく対応すれば大丈夫です。
もし税務調査でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。一緒に乗り切りましょう!