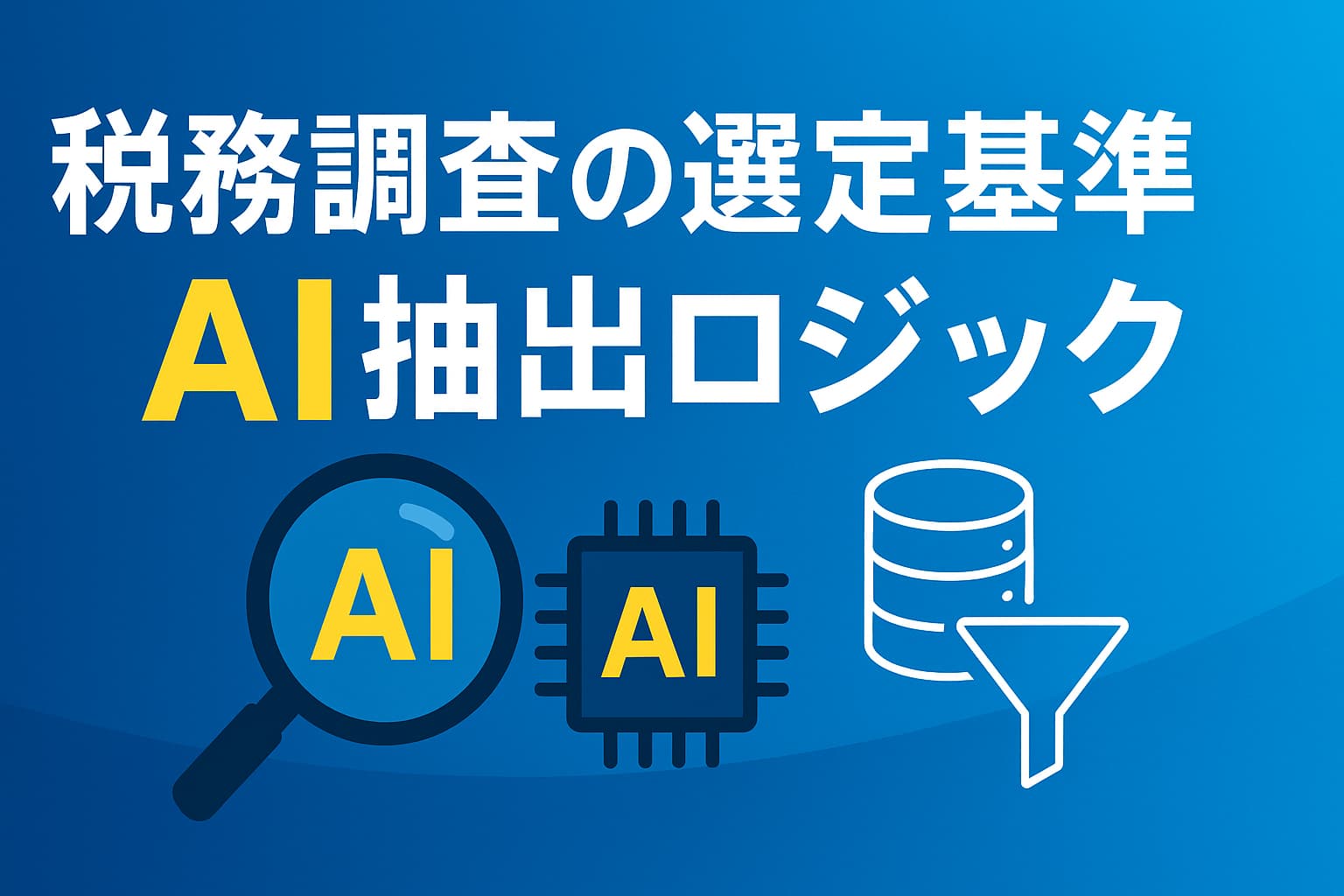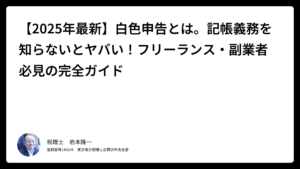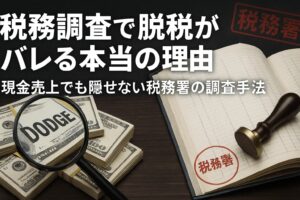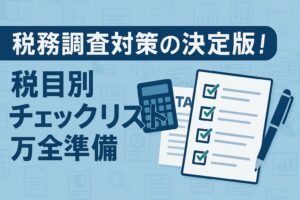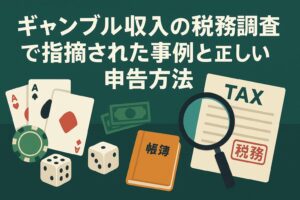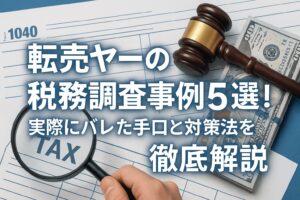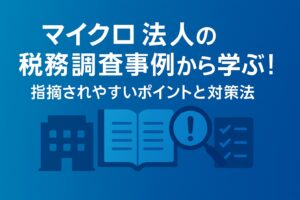みなさんこんにちは、税理士の岩本隆一です。無申告や税務調査を多く取り扱っている税理士事務所を営んでいます。(いつでもお問い合わせください!!)
ぶっちゃけ聞きます。「税務調査」って怖くないですか?
「なんで自分のところに来るんだよ…」「何を見られるんだろう…」
そんな不安、わかります。今日は「アイツはなぜマークされるのか」という謎に迫ります。特に最近話題の「AI活用」がどう関係しているのか?本記事を読めば、あなたの会社がどれくらい「マークされやすいか」が分かるようになりますよ。
税務調査って、ぶっちゃけ何のためにあるの?
「お上が庶民からお金を巻き上げる仕組み」だと思っている人、正直に手を挙げてください🙋♂️
実は違います(まあ、少しはそういう側面もあるかもしれませんが)。
税務調査の本質は「公平性の担保」です。真面目に納税している人が「あいつだけズルいよね」と思わないようにするための仕組みなんですね。国税庁の公式見解では「大口・悪質な不正計算を重点的に」と言っています。
でもね、現実はどうでしょう?
🔍 売上1000万円未満の小さな会社も普通に調査が入る
なぜ?
それはズバリ、テクノロジーの進化です。KSKシステムやAIの導入で、「小さくても怪しい」と判定された納税者を見つけ出せるようになったんです。規模より「不正の匂い」を優先するようになってきているんですね。
「マークされやすい会社」の特徴!あなたはいくつ当てはまる?
財務上の「ここ怪しくね?」パターン
ぶっちゃけ、一番マークされやすいのは「数字が変」な会社です。国税のAIくん(と調査官)は、こんなパターンを見つけるとニヤリとします👀
✅ 売上が前年比で「急に増えた」「急に減った」(特に説明できない理由で)
✅ 交際費・外注費など特定の経費がやたら多い(「何に使ったの〜?」案件)
✅ 同業他社より利益率が激しく低い(「本当にそんなに儲からないの〜?」)
✅ 毎年の利益がキリよく100万円前後(「調整してます感」満載)
✅ 長年赤字だったのに突然黒字化(「どうやったの?教えて〜」)
これらの特徴がある会社は、国税サイドから見ると「おいしそうな獲物」に見えるんです。「調べたら何か出てくるんじゃね?」と思われているわけですね。
「1000万円の壁」問題 —— これは絶対に知っておくべき❗
個人事業主には「消費税の壁」があるの、皆さん知ってますよね?
売上1000万円を超えると消費税の課税事業者になります。これって8%や10%を納める必要が出てくるので、正直めちゃくちゃ痛い。
で、多くの個人事業主がやっちゃうのが…
「毎年の売上を990万円くらいで抑える」
🚨 これ、国税庁からしたら”怪しさMAX”なんです!
「絶対に売上隠してるよね?」と思われちゃうんですね。実際、私のお客さんでも「なぜか売上が毎年990万円」という人の所に調査が入り、バッチリ追徴課税された例があります。
売上が990万円前後の人、特に5年連続とかで「奇跡の990万円」を記録している方は要注意です。国税庁のAIくんはあなたを見つめています👁️
現金商売のみなさん、お気をつけください💸
現金商売の方々、耳の痛い話かもしれませんが…
「現金商売 = 怪しい」
…という悲しい等式が国税庁の中に存在します。飲食店、小売店、美容院、建設業など現金取引がメインの業種は「売上をごまかしやすい」と思われがちなんですね。
実際、統計でも「申告漏れ発見率が高い業種」として次のようなものが挙げられています:
🔴 バー・クラブ(「あのボトル代はどこへ…?」)
🔴 経営コンサルタント(「本当にそんなに報酬もらったの?」)
🔴 建設業(「現金払いの工事はどこへ…?」)
最近では、国税庁の「新たなターゲット」も出てきています:
💰 暗号資産(ビットコインなど)取引者
💰 YouTuberなどのインターネット事業者
💰 「ギャラ飲み」などのグレーゾーンビジネス
こういう「新しい形の現金商売」は特に監視対象になりやすいです。「どうせバレないでしょ」は通用しなくなってきています!
税理士いないの?そりゃマークされますよ🤷♂️
「税理士なんて雇う余裕ないよ〜」
自分で全部やっちゃってる人、多いですよね。でもこれ、国税庁的には「あら、税理士のチェック入ってないのね👀」というサインなんです。
「素人の自己流申告=間違ってそう」と思われがちです。
他にも次のような会社はターゲットになりやすいですよ:
⏰ 長期未調査組:6年以上税務調査を受けていない(「そろそろ見に行くか〜」)
🔄 前科持ち:過去の調査で申告漏れを指摘された(「また同じことやってないかな〜」)
実は税務調査って「ランダム」じゃないんです。「調査確率が高い」パターンに当てはまる人から順番に狙われていくシステムなんですね。
KSKシステム:国税庁の「監視の目」の正体
知られざる「税務調査の裏側」 —— KSKシステムの恐怖
みなさん、国税庁が「超巨大なビッグブラザー」になっていることをご存知ですか?
その名も「KSKシステム」(国税総合管理システム)。
これは全国の税務署をネットワークで結び、あなたの申告・納税情報をすべて一元管理するシステムです。1995年から導入が始まり、2001年に全国展開されました。
このシステム、あなたのこんな情報を「全部」知っています👇
📋 あなたの基本情報:名前、住所はもちろん、マイナンバーも
💰 申告書の細部:過去何年も前の申告内容まで丸見え
💴 納税・還付履歴:「あの時いくら納めた/還付された」が全部記録
🔍 過去の税務調査結果:「前回何を指摘されたか」も記録済み
📝 法定調書:会社からの給与、取引先からの支払いなど第三者情報も完備
🌏 海外送金記録:「海外に資産隠してるでしょ?」もバレる
👥 関連する人・会社の情報:「この人と関係あるあの会社」も把握
国税庁はあなたのことを「驚くほど」知っているんです。怖くないですか?
KSKシステムがあなたを「マーク」する仕組み
KSKシステムは、あなたのデータを様々な角度から「審査」して、「コイツ、調査したら何か出てきそう!」という人を抽出します。
どんな風に判断しているのか?具体的な「マーク」ロジックをご紹介します👇
- 経年比較(「あれ?去年と全然違うぞ?」)
→ 前年と比べて売上や経費が急に変わった会社をマーク - 整合性チェック(「あれ?話が合わないぞ?」)
→ 申告書の中で数字の辻褄が合わない会社をマーク - 同業他社比較(「なんでこの会社だけ儲からないの?」)
→ 同じ業種なのに利益率が極端に低い会社をマーク - 特定条件抽出(「この条件の会社は怪しい!」)
→ 売上が990万円くらいの会社などをマーク - リスクスコアリング(「この会社の怪しさレベルは87点!」)
→ 上記の結果から「税務調査した方がいい度」を点数化
でも、初代KSKにも弱点がありました。「縦割り」で作られていたため、例えば「法人税の申告」と「役員の所得税申告」を突き合わせて矛盾を見つけるのが難しかったんです。
この弱点を克服するのが、次世代システム「KSK2」と、AIの導入なんです。ここからが本番です…😱
AI時代の到来:税務調査選定の革命
国税庁のDXとAI戦略
国税庁は「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション」を掲げ、AIの活用と次世代KSKシステム(KSK2)の開発を進めています。KSK2は令和8年(2026年)頃の本格稼働を目指しており、以下のような特徴を持つ予定です:
- 統合データベース:税目・事務系統を超えたデータの一元管理
- オープンなシステム基盤:柔軟性・拡張性の高いアーキテクチャ
- 高度なAI・分析機能:機械学習による申告漏れリスク判定
- AI-OCR導入:紙申告書の効率的データ化
興味深いのは、国税専門官採用試験に「理工・デジタル系」区分を新設し、ICTやデータ分析の専門人材を積極採用している点です。税務調査官の仕事も、AIと共存する形へと変わりつつあります。
AIの「餌」となるデータの恐怖 —— あなたのプライベートも丸見え?
AIの最大の恐ろしさは「何でも食べる」ところです。国税庁のAIは、あなたに関する様々なデータを「餌」にして強くなっていきます。
もはや税務申告だけでなく、あなたの生活全体が監視対象になっているんです。
👁️ AIが「食べている」データの種類
- 公開情報:あなたの会社HP、ニュース、SNS投稿も監視対象(「インスタでハワイ旅行アップしてるけど、この所得で行けるの?」)
- 業界データ:同業他社の平均値と比較(「なんでこの飲食店だけ利益率5%なの?同業は15%あるよ?」)
- 役所情報:他省庁のデータも連携(「この人、高級マンション買ったみたいだけど所得と合わないな?」)
特に怖いのがSNSとAIの組み合わせです。
「インスタで高級レストランの投稿を頻繁にしているのに、申告所得は年300万円…?」というような矛盾を、AIが自動検出する時代がすぐそこまで来ているんです。
あなたのSNS、大丈夫ですか?税務調査官に見られても問題ない投稿内容になっていますか?思わぬところから「マーク」される可能性があるんです。
学習する能力へと進化している点です。単純な「IF-THEN」ルールでは捉えきれない巧妙な不正パターンも、AIなら検出できる可能性があります。
AIの成績は脅威的! —— 「マーク」された企業の末路
国税庁のAIはすでに実戦で稼働し始めていて、その成績は脅威的なんです。
あるレポートによると、AIが選定した調査対象からは平均547万円もの追徴税額が取れているそうです。これは一般の調査平均(386万円)より40%以上も高い!
つまり、「AIのマークした会社」は「人間がマークした会社」よりも高確率で申告漏れが見つかっているということです。
AIは全然ミスらないんですね…😨
調査官の役割も変わってきています。AIが「この会社怪しいよ!」と言ったら、調査官はその会社を徹底的に調べる。単純なチェックはAIに任せて、人間はより深い追及に集中する。
そんな「AIと人間のタッグ」が完成しつつあるんです。もはや逃げ場はありません…。
世界の税務AIの恐怖 —— 「先進国」はみんなやってる
こんな恐ろしいAI税務調査は日本だけの現象じゃありません。世界中の税務当局が同じようなテクノロジーを導入しています。これはもはや「グローバルな流れ」なんです。
国別にどんな「恐ろしいこと」をやっているのか見てみましょう:
🇸🇬 シンガポール:「Ask Jasmine」というAIチャットボットを導入。 「ねえJasmine、法人税について質問があるんだけど」と聞くと、AIが自動回答。その裏では、あなたがどんな質問をしたかも全部記録されてるんですよ。「この人、こんな質問してるってことは何か隠してるかも?」なんて分析されてるかも…。
🇨🇦 カナダ:申告書を自動チェックして、リスクの高い申告書だけを抽出。 銀行からの情報と申告内容を自動で照合して「あれ?口座には100万入ってるのに申告は50万?」みたいな矛盾を即座に発見。
🇺🇸 アメリカ(IRS):滞納者への最適アプローチを自動判定。 「この人には優しく手紙を送ろう」「この会社にはいきなり差押えだ!」みたいな判断をAIが実施。人間味のかけらもありません…。
🇦🇺 オーストラリア:リアルタイムでの第三者データ照合。 給与や配当の情報が入った瞬間に「あれ?申告してないじゃん?」とチェック。逃げる暇すらありません。
日本のKSK2開発はこうした世界的な流れの中にあります。日本の特徴は「基盤整備を優先」していること。他国が「とりあえずチャットボット作っちゃおう!」みたいな個別施策を先行させる中、日本は「まずはデータベースをしっかり作ろう」というアプローチ。
小さく早く始めるか、大きくじっくり始めるか、の違いですが、目指す先は同じ。「逃がさない税務システム」の構築です…😨
AIの恐ろしい欠点 —— 「ブラックボックス」問題
AIにも大きな問題点があります。最大の問題は「ブラックボックス問題」です。
AIが「この会社を調査しろ」と判断する理由は、もはや人間には完全に理解できない場合があります。複雑な機械学習モデルの中で何が起きているのか、開発者ですら正確には把握できないんです。
これって怖くないですか?
あなたは突然「AIがあなたを選びました」と言われても、なぜ選ばれたのか理由がわからない。反論のしようがありません。
税務調査を受ける納税者にとっては大問題です。「なぜ自分が調査対象になったのか」がわからなければ、調査の妥当性を判断したり、誤りを指摘したりすることもできません。
法的にも問題です。税務調査には「調査の必要性」という法的要件がありますが、AIの判断理由がブラックボックスだと、その「必要性」をどう説明するのか?
そもそも「公平な課税」と言いながら、AIが特定の業種や納税者層を不当にターゲットにしていないという保証はあるのでしょうか?
さらに、AIが誤った判断をした場合、責任はどこにあるのか?これらの問題に対して、国税庁からの明確な回答はまだありません…。
AI時代の税務調査対策 —— 今すぐ始めるべき「防衛策」
ここまで読んで「もう逃げ場がない…」と絶望したあなた。
大丈夫です。AIには弱点もあります。AIを欺くことはできないかもしれませんが、AIに「あなたは怪しくない」と判断させることはできます。
AI対策の基本:「整合性」がすべて
AI時代の最重要ポイントは「データの正確性と一貫性」です。
AIは様々なデータを横断的に分析し、「おかしな点」を見つけるのが得意。逆に言えば、すべてのデータに矛盾がなければ、AIの「怪しい」判定を回避できる可能性が高まります。
具体的な対策を紹介します👇
1. 緻密な記録管理 —— AIを「安心」させよう
✅ 取引が発生したその日に記帳する習慣をつける
✅ 会計ソフトを導入して「人為的ミス」を減らす
✅ 記帳ルールを統一する(経費の計上方法など)
AIは「規則性」が大好き。毎月きっちり同じタイミング、同じルールで記帳されている会社は「真面目そう」と判断されやすいです。
2. 証拠書類の完璧な保管 —— 「証拠」で身を守る
✅ すべての取引の証憑書類を整理して保管
✅ 特に金額の大きな取引は複数の証拠を準備
✅ 交際費など曖昧になりがちな経費は詳細記録を残す(誰と、どこで、なぜ)
「言った言わない」の争いでは国税に勝てません。客観的な証拠があれば、AIが「怪しい」と判断しても、人間の調査官を納得させられる可能性が高まります。
3. 自己データのチェック —— AI的視点で自分を見る
✅ 申告前に財務データを客観的にレビュー
✅ 「前年比で急変した項目」をチェック
✅ 業界標準から大きく乖離していないか確認
AIが見ているのと同じ視点で自分のデータを見てみましょう。「この数字、AIが見たらどう思うだろう?」と考えることで、リスクを事前に把握できます。
4. 閾値への過剰な接近を避ける —— 「意図的操作」と思われるパターンを避ける
✅ 売上が毎年990万円ちょうどになるような不自然な調整は避ける
✅ 利益率が毎年キリよく同じ数字になる不自然さを避ける
「明らかに意図的」と思われるパターンはAIの大好物です。自然な数字の揺れがある方が逆に不自然じゃなく見えます。
5. そもそも不正はしない —— AIの検出能力は年々向上
✅ 売上除外、架空経費計上などの意図的な不正はAIに発見されるリスクが極めて高い
✅ 発覚した場合の重加算税などのペナルティは非常に重い
言うまでもありませんが、そもそも不正自体をしないことが最大の対策です。AI時代には「バレないだろう」はもはや通用しません。
税理士という「盾」 —— AIに立ち向かう最強の味方
AI時代において、税理士の役割はこれまで以上に重要になっています。なぜなら、冷徹なAIに対抗できるのは、専門知識と経験を持った「人間の知恵」だからです。
税理士は次のような点であなたを守ってくれます:
💪 正確な申告サポート
最新の税法や判例を踏まえた正確な申告書作成をサポート。AIが「怪しい」と判断するポイントを事前に潰せます。
🔍 リスク事前診断
あなたの申告内容を「AIの目線」で事前チェック。「この部分、説明できる?」というリスク洗い出しが可能です。
📝 適切な書類管理指導
「この取引はこういう証拠を残しておくべき」など、AI時代に耐える書類管理方法を指導してくれます。
🛡️ 調査対応の盾
万が一、調査が入った場合も、専門家として適切に対応し、あなたを守ってくれます。
「書面添付制度」—— 税理士の最強の武器
特に有効なのが「書面添付制度」です。
これは、税理士が申告書に「私が申告内容をチェックしました」という書面を添付する制度。この書面があると、調査前に必ず税理士に意見を聞く機会が設けられます。
この段階で税理士が「この数字になった理由はこうです」と適切に説明できれば、実地調査に進まずに済む可能性が高まります。
AIが「この会社の利益率、同業他社より低すぎ!怪しい!」と判断しても、税理士が「これには正当な理由があります。具体的には…」と説明することで、無駄な調査を防げるんです。
定量的なAIの判断に、定性的な専門家の判断をぶつける。これが最強の防衛策なのです。
まとめ:AI時代の税務調査を生き抜く「3つの鉄則」
いかがでしたか?国税庁のAI化は着々と進んでいて、もはや「逃げ場がない」状況に近づいています。
でも、絶望する必要はありません。結局のところ、AI時代を生き抜く秘訣は「正しいことをきちんとやる」に尽きます。
最後に「AI時代の税務調査を乗り切る3つの鉄則」をお伝えします
鉄則1:「整合性」がすべて
AIは「データの矛盾」を見つけるのが得意です。逆に言えば、すべてのデータに整合性があれば、AIのチェックをパスできる可能性が高まります。日々の記帳を正確に行い、取引証拠をきちんと保管しましょう。
鉄則2:「自然さ」を心がける
AIは「不自然なパターン」に敏感です。売上が毎年ぴったり990万円とか、利益率が毎年キリよく同じ数字になるような不自然さは避けましょう。正直な申告をしていれば、多少数字に揺れがあるのは当然です。
鉄則3:「専門家」と連携する
AI時代こそ、「人間の知恵」が重要です。税理士というプロの力を借りて、申告前のリスクチェック、書面添付制度の活用など、AIに対抗できる「人間的な説明力」を確保しましょう。
税務行政のAI化は今後も加速することでしょう。KSK2の本格稼働(2026年予定)も近づいています。この流れに対応するためには、「正直な申告」と「きちんとした記録管理」という基本に立ち返ることが最も有効な戦略です。
当事務所では、AI時代の税務調査対策、無申告対応など、税務に関するあらゆるご相談をお受けしております。「なぜ自分が調査対象になったのか?」「AI時代にどう備えるべきか?」など、お悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。専門的な観点から最適なアドバイスをご提供いたします!!