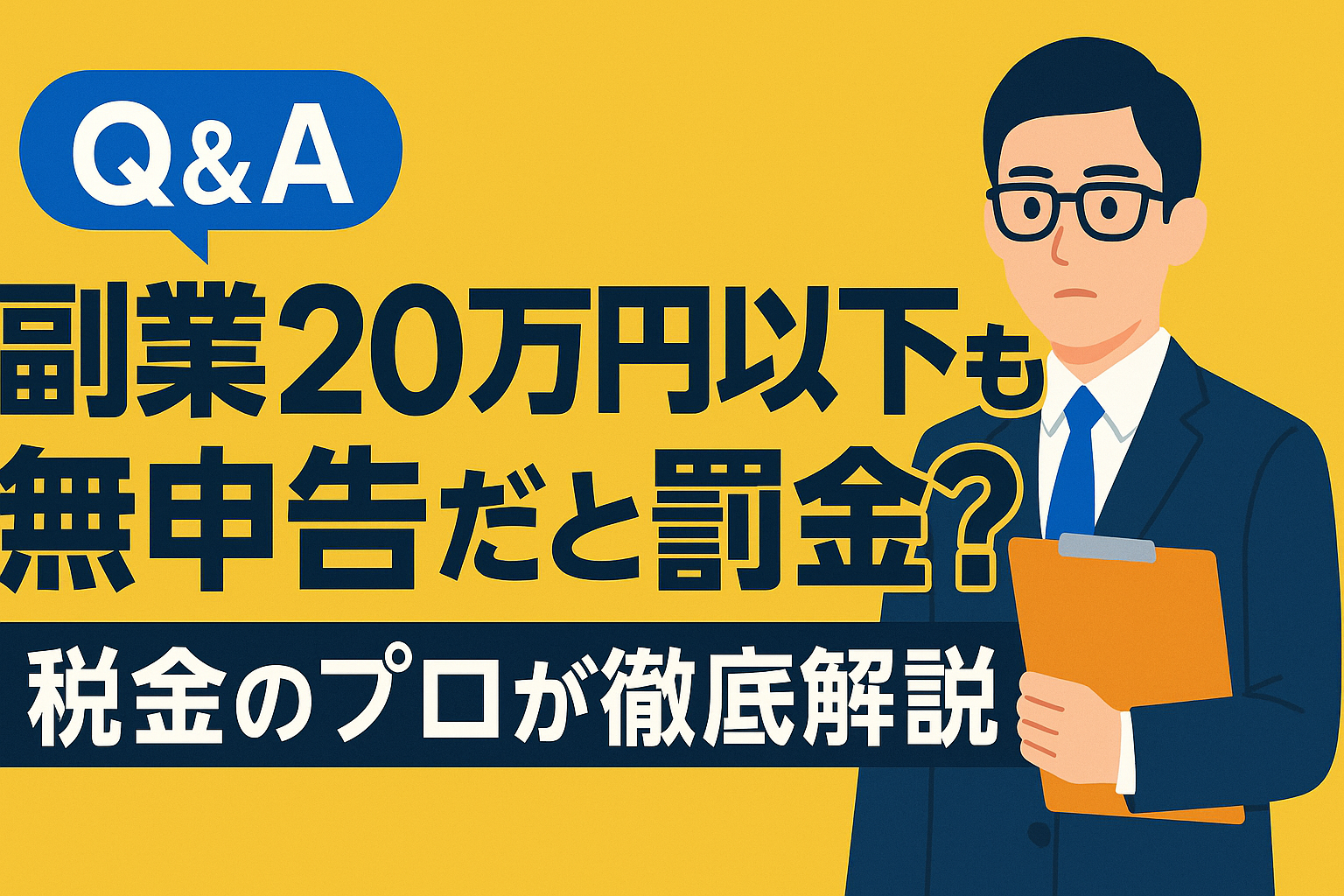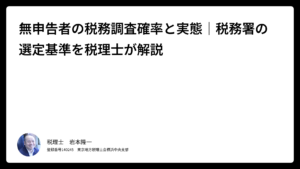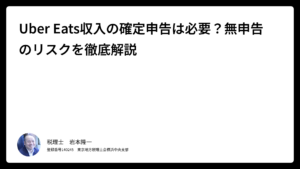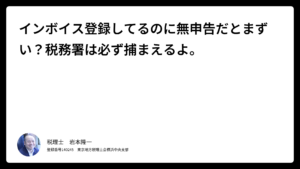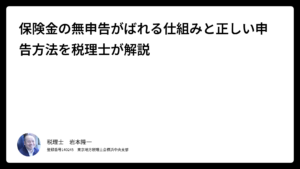みなさんこんにちは、税理士の岩本隆一です。無申告や税務調査を多く取り扱っている税理士事務所を営んでいます。(いつでもお問い合わせください!!)
「副業の所得が20万円以下なら確定申告不要でOK!」
これ、マジで危険な半分だけの知識です。
私の事務所には毎年、この「20万円ルール」を信じて数年間無申告を続けた結果、突然の追徴課税や延滞金に青ざめる方が何人も相談に来ます。中には会社にバレて転職を余儀なくされた人も…😱
今日は完全に誤解されがちな「副業の20万円ルール」について、知らないと絶対に損する情報を徹底的に解説します。5分で読めるので最後まで目を通してください!
「20万円ルール」がほぼ全員に誤解されている件
「副業の所得が20万円以下なら確定申告不要」というルール、本当は超重要な条件がついています。
これ、所得税の確定申告だけが免除されるルールなんです。住民税の申告は関係ありません!!
でも世の中の解説の99%がこの点を明確に書いていないので、多くの人が「税金すべて申告不要」と勘違いしちゃうんですよね。
「収入」と「所得」の違い、わかります?
まず理解してほしいのは「収入≠所得」という超基本です。
- 収入 = お金が入ってきた総額(売上)
- 所得 = 収入 – 必要経費(利益)
例えば:
- メルカリで年間35万円売上げて、仕入れや送料で20万円使った→所得は15万円
- ブログ収入が22万円あって、サーバー代や参考書代で3万円使った→所得は19万円
つまり、収入が20万円超でも、所得が20万円以下ならこのルールは適用される可能性があります。逆に、経費があまりない場合は収入=所得になるので注意!
住民税の申告を忘れると超ヤバい
ここからが本当に重要です。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必須です。副業の利益が1円でもあれば、原則として住民税を申告する義務があります!!
これを知らずに無申告を続けると…
- 住民税の追徴課税+延滞金が発生
- 場合によっては本業の会社に副業がバレる
- 国民健康保険料などが正確に計算されず、後から請求される
「え?それなら最初から確定申告したほうが楽じゃん…」と思いますよね。そうなんです。実は多くの場合、20万円以下でも確定申告したほうが総合的にラクなんです。
俺の友人が20万円ルールで痛い目にあった話
実際にあった話です。
私の友人Aさん(30代SE)は、副業でプログラミング講師のアルバイトをしていました。年間の報酬は15万円ほど。
「20万円以下だから申告不要でしょ」と3年間無申告。
ある日、会社の経理部長から呼び出されて「なぜ副業をしているのに申告していないのか」と問い詰められました。
原因は住民税の特別徴収通知書。通常より住民税額が高いことから副業の存在がバレたのです。
結局、Aさんは会社の副業禁止規定に抵触したとして始末書を書くことに。さらに市役所からは過去3年分の住民税の修正申告を求められ、本税+延滞金で5万円以上支払うハメになりました。
たかが15万円の副業収入が、こんな大問題に…😱
所得20万円以下でも確定申告が必要なケース、知ってた?
以下のようなケースでは、副業所得が20万円以下でも確定申告が必要になります:
- 本業の給与収入が2,000万円を超える場合 (年収2,000万円超の方は20万円ルール対象外です!)
- 医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合 (この場合、副業所得も含めて全部申告する必要アリ!忘れると後で痛い目に遭います)
- 副業から源泉徴収されてる場合 (確定申告で税金が戻ってくるかも。やらないと損するケースも!)
特に2つ目は要注意です。例えば、35万円の医療費控除を受けるために確定申告したのに、副業所得18万円を申告し忘れると、後から修正申告が必要になります。ペナルティも発生するかも…😱
副業が会社にバレる仕組み、9割の人が知らない
副業をしている方の最大の恐怖「会社にバレるかも…」問題。
実は副業が会社にバレる最も一般的な経路は住民税の仕組みです。
多くの会社では、毎月の給与から住民税を天引きする「特別徴収」を行っています。市区町村は前年の所得(本業+副業)に基づいて住民税額を計算し、その情報を会社に送ります。
ここで経理担当者が「あれ?🤔この人の住民税額、給与の割に高くない?」と気づくと、副業の存在を疑われるわけです。
実際、私の顧問先企業でも「住民税額の不自然な増加」をきっかけに副業が発覚するケースが年に数件あります。
対策:「普通徴収」への切り替えで会社バレを防ぐ
これを回避する方法があります。住民税の「普通徴収」(自分で納付する方式)への切り替えです。
確定申告をする場合は、申告書第二表の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選択。住民税申告のみの場合は、申告書の同様の欄をチェックするか、市区町村窓口で相談してください。
ただし、これも万能ではありません:
- 普通徴収への切り替えが必ず認められるわけではない
- 副業がアルバイト(給与所得)の場合は効果薄い
- 自分で納付を忘れると延滞金が発生するリスクあり
無申告のペナルティ、バカにできない金額です
「副業の所得なんて少額だし、バレても大したことないでしょ」
これ、超危険な考え方です!実際のペナルティを見てみましょう:
所得税(国税)のペナルティ
- 無申告加算税:納税額の15%〜30%
- 延滞税:年率2.4%〜8.7%程度
住民税(地方税)のペナルティ
- 延滞金:国税の延滞税に準じた利率
例:副業所得18万円、税率10%と仮定すると年間の住民税約1.8万円。 これを3年間無申告だと、本税5.4万円+延滞金で合計7万円程度になることも…!
「たかが副業」が「されど副業」に変わる瞬間です😱
税務署は「副業の無申告」をどうやって見つける?
「少額の副業なんて見つからないでしょ」
これ、昔は多少は通用したかもしれませんが、今はもうムリです。なぜなら:
- 支払調書:フリーランス報酬を支払った企業は「誰に、いくら支払ったか」の情報を税務署に提出します。クラウドソーシングやスキルシェアサービスなども対象です!
- マイナンバー制度:様々な収入情報が紐づけられる時代に。金融口座もマイナンバーと紐づくようになれば、さらに把握率アップ。
- 銀行口座の調査:税務署は、法律に基づき銀行に情報照会できます。定期的な入金があると怪しまれることも。
- 税務調査:あなたの取引先が税務調査を受けると、芋づる式にバレることも。
- タレコミ:意外と多いのが「知人からの通報」。SNSでの自慢投稿が発端になることも…😱
実際、私の事務所に相談に来る方の半数以上は「もう税務署にバレてる」状態です。DXが進む今、「バレない」という希望的観測は捨てましょう。
副業の「所得」計算、正しくできてる?
所得を正確に計算するには、何が経費になるかを知る必要があります。
経費になるもの
- 商品仕入れ代・材料費(物販の場合)
- 副業に使うPC・カメラなどの減価償却費
- 業務用の通信費(家事按分必要)
- 副業スペースの家賃(家事按分必要)
- 広告宣伝費・業務関連書籍
- 支払手数料(例:PayPal手数料)
経費にならないもの
- 個人的な食事代、服(仕事兼プライベート用)
- 所得税・住民税
- 保険料(事業用の保険を除く)
- 通勤費(副業がアルバイトの場合)
特に自宅兼用の費用は「家事按分」が必要です。例:自宅の10%を副業に使用→家賃や光熱費の10%を経費計上可能。
適当に経費計算すると税務調査で否認されるリスクがあるので、記録はしっかりと残しておきましょう!
副業税金、正しい対応方法4ステップ
副業をする上で、以下の対応を徹底するだけで9割の問題は防げます:
- 収支記録は必ず残す:無料アプリでもOK。日付・相手・金額・内容を記録
- 領収書等は7年保管:スマホで撮影してデータ保存するのもアリ
- 毎年適切に申告する:確定申告または住民税申告を必ず期限内に
- 迷ったら専門家に相談:「知らなかった」は通用しません!
私が初めて副業を始めたとき、Excel一つでいい加減に管理→税務調査で経費否認→追徴課税…という苦い経験をしました。皆さんには同じ思いをしてほしくありません。
まとめ:正しい知識で副業を安全に楽しもう!
副業の税金、特に「20万円ルール」について解説しました。最後に重要ポイントを再確認:
- 20万円ルールは所得税の申告免除だけ:住民税はほぼ確実に申告必要
- 所得=収入-経費:この計算を正確に!
- 確定申告が必要なケースを把握:医療費控除等と併用時は要注意
- 会社バレ防止は普通徴収:100%ではないが一定の効果あり
- 記録と保管は義務:税務調査対策として必須
「20万円以下だから安全」「申告しなくても大丈夫」という甘い考えは、将来の大きなリスクになります。正しい知識で、安心して副業ライフを楽しみましょう!
当事務所ではいつでも相談をお請けいたしております。副業の税金で悩まれている方は、お気軽にご連絡ください!