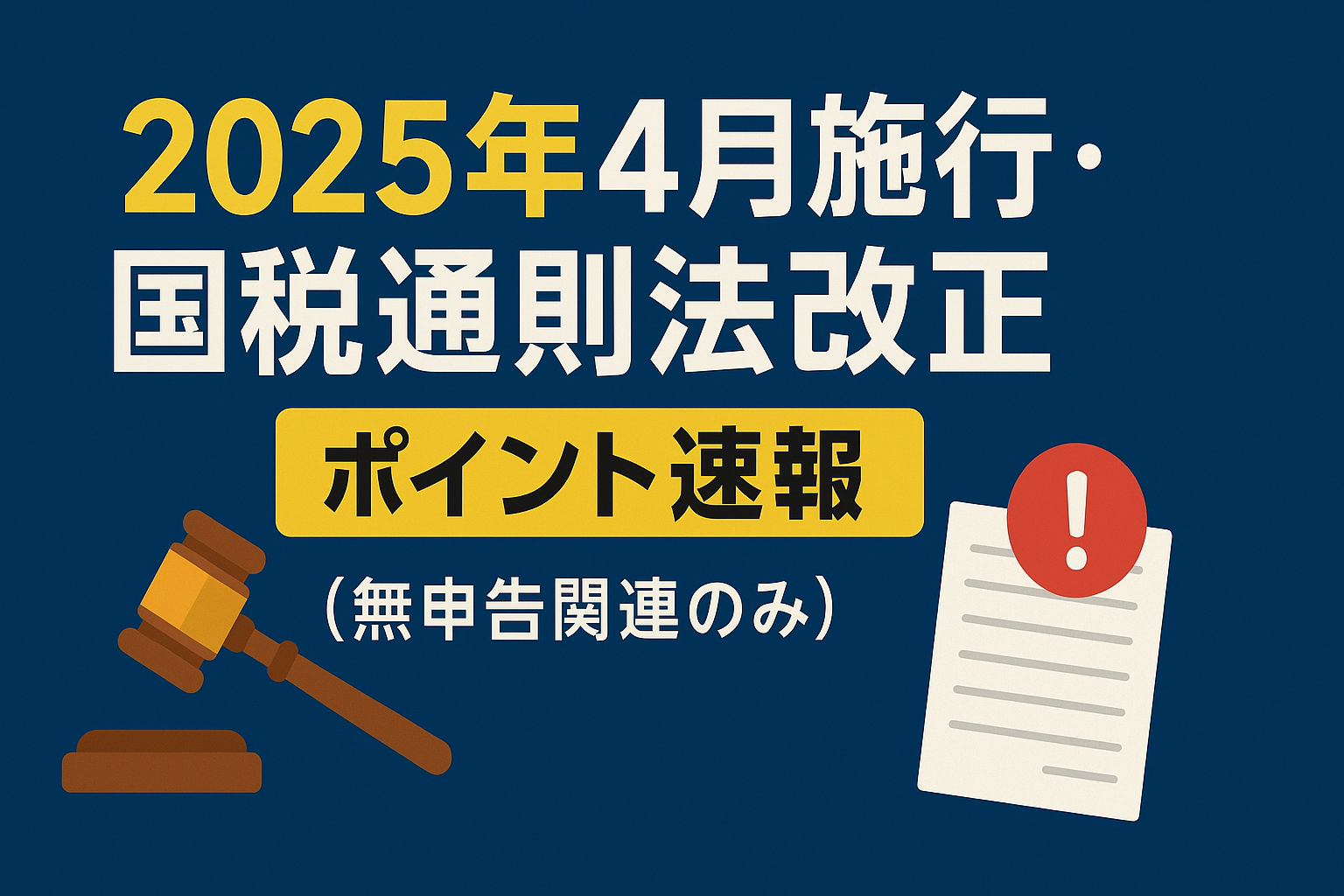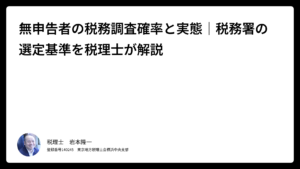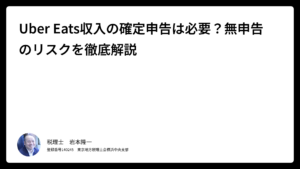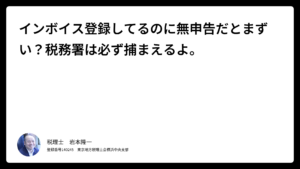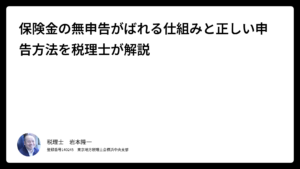みなさんこんにちは、税理士の岩本隆一です。無申告や税務調査を多く取り扱っている税理士事務所を営んでいます。(いつでもお問い合わせください!!)
「え、無申告ってそんなにヤバかったの?」という人のための最新改正情報
税金の話って正直めんどくさいですよね。でも、知らないとあとで大変なことになるのが税金の恐ろしいところ。
特に「無申告」については、2024年1月と2025年1月に施行された国税通則法の改正で、ペナルティがかなり厳しくなりました。2025年4月にも関連する施行規則等の改正が行われていますが、基本的な仕組みは2024年・2025年の改正で既に固まっています。
この記事では、「無申告のペナルティって具体的にどう変わったの?」という疑問にお答えします。
「無申告」の基本おさらい
まず「無申告」って何?という超基本から。
「無申告」とは、所得税や法人税、消費税などの確定申告を、法定申告期限までに行わないことです。
例えば、個人の所得税なら毎年3月15日、法人税なら事業年度終了後2ヶ月以内が基本的な申告期限。これを過ぎても申告しないと「無申告」状態になります。
改正前は、無申告が発覚したら主に以下のペナルティがありました:
- 無申告加算税: 本来納めるべき税額の15%(50万円超の部分は20%)
- 重加算税: 悪質な場合(隠蔽・仮装)は40%
- 延滞税: 法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じた利息相当額
簡単に言うと「本来の税金+ペナルティ+利息」を払わされる、ということですね。
改正の3大ポイント
では本題。今回の改正で何が変わったのか?主に3つのポイントがあります。
ポイント1:高額無申告は税率アップ(2024年1月1日施行)
「自営業者だけど確定申告めんどくさいから放置しとこ」とか「副業の収入は申告しなくてもバレないだろ」と考えてる人は要注意です。特に金額が大きい場合、ペナルティがさらに重くなりました。
具体的には:
無申告加算税の税率
- 50万円以下の部分:15%(変更なし)
- 50万円超300万円以下の部分:20%(変更なし)
- 300万円超の部分:30%(改正でアップ)
たとえば、1,000万円の無申告が発覚した場合:
改正前:
- 50万円×15% + 950万円×20% = 7.5万円 + 190万円 = 197.5万円
改正後:
- 50万円×15% + 250万円×20% + 700万円×30% = 7.5万円 + 50万円 + 210万円 = 267.5万円
単純計算で70万円もペナルティが増加します。お金持ちほど無申告のリスクが高まった、ということですね。
「えっ、そんなに払えない!」と思った方、残念ながらこれは既に施行されています(2024年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用)。
ポイント2:繰り返し無申告はさらに重罰(2024年1月1日施行)
「まあ、1回くらいなら…」という甘い考えも危険です。短期間に無申告を繰り返すと、さらに重いペナルティが科されます。
具体的には:
前年度および前々年度に同じ税目で無申告加算税または無申告に係る重加算税を課されていた場合、今回の無申告に対するペナルティに一律10%加重されます。
つまり:
- 50万円以下の部分:15% → 25%
- 50万円超300万円以下の部分:20% → 30%
- 300万円超の部分:30% → 40%
- 無申告に係る重加算税:40% → 50%
こうなると、本来の税額の半分近くがペナルティとして上乗せされることになります。恐ろしい…。
これも既に施行済み(2024年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用)なので、過去に無申告を指摘されたことがある方は特に注意が必要です。
ポイント3:悪質な無申告はさらに制裁強化(2025年1月1日施行)
「まあ、バレなきゃいいや」と隠したり偽装したりすると、さらに厳しい措置が待っています。
例えば:
- 無申告に「仮装・隠蔽」(帳簿の改ざんや架空経費の計上など)があれば、重加算税40%(繰り返しなら50%)
- 更正の請求(税金の還付を求める手続き)での「仮装・隠蔽」も重加算税の対象に(2025年1月1日から)
- 法人の役員が不正に関与した場合、法人が払えなければ役員個人が納税義務を負う可能性(第二次納税義務)
「会社を倒産させて税金逃れよう」とか「架空経費で還付金もらおう」とか考えている人は、個人の財産まで追及される可能性があるということです。
「2025年4月施行」って何が変わるの?
さて、本記事のタイトルにもある「2025年4月施行」の改正ですが、2025年3月31日に公布された国税通則法施行令(令和7年政令第126号)や国税通則法施行規則(令和7年財務省令第25号)等が、原則として同年4月1日から施行されています。
ただし、これらは前述した無申告ペナルティの基本構造を変更するものではなく、むしろ運用のための手続き的な詳細や、他の税制改正に伴う調整に関連するものです。
例えば:
- 申告書様式の変更
- 電子申告システムの改修
- 事務運営指針の変更
- 所得控除の見直しに伴う調整
- 電子帳簿保存法の関連措置
また、GビズID連携によるe-Taxの利便性向上や、処分通知等の電子交付の段階的な拡充など、納税環境のデジタル化に関連する施策も含まれています。
一般の納税者にとっては、2024年1月と2025年1月に施行された無申告ペナルティの基本構造を理解することが最も重要です。手続きや様式については、国税庁からの最新情報を確認するとよいでしょう。
ペナルティを避けるには?自主的な行動が鍵
「やばい、申告忘れてた!」という方、すぐに行動すれば救済措置があります。
自主的な期限後申告がベスト
税務署に指摘される前に自ら申告すると、無申告加算税が大幅に軽減されます:
- 税務署から連絡が来る前に自主的に申告:無申告加算税5%
- 税務調査の通知後に申告:無申告加算税10%/15%/25%
- 調査後に決定を受けた場合:無申告加算税15%/20%/30%
さらに、厳しい条件ですが、無申告加算税が課されないケースもあります:
- 法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告を行う
- 本来の法定納期限までに税金を全額納付している
- 過去5年間に無申告加算税等を課されていない
ただし、延滞税は別途発生するので注意が必要です。
時効を期待するのはNG
「5年経てば時効になるから放置しよう」という考えも危険です。
確かに税金を徴収する権利には時効があり、原則として法定申告期限から5年で消滅します。しかし、偽りその他不正の行為(脱税)があった場合は、時効が7年に延長されます。
時効を待っている間に発覚したら、延滞税が膨大な額になる可能性があります。リスクが大きすぎるので、おすすめできません。
こんなケースはどうなる?具体例で見る改正の影響
実際にどんな影響があるのか、具体例で見てみましょう。
ケース1:個人事業主の副業収入無申告
フリーランスのAさんは、本業の他にネット副業で年間500万円の所得を得ていましたが、確定申告をしていませんでした。令和6年(2024年)分の申告について、令和7年(2025年)に税務調査で指摘され、納付すべき所得税額が80万円と判明しました。
適用されるペナルティ:
無申告加算税:
- 50万円×15% + (80万円-50万円)×20% = 7.5万円 + 6万円 = 13.5万円
- 延滞税も別途発生
もしAさんが令和4年分、令和5年分も無申告だったら?
- 10%加重で、50万円×25% + 30万円×30% = 12.5万円 + 9万円 = 21.5万円
- ペナルティが13.5万円 → 21.5万円に増加!
もし税務調査前に自主申告していたら?
- 無申告加算税は80万円×5% = 4万円に軽減
- 9.5万円もの節約になる!
ケース2:法人の売上除外が調査で発覚
B株式会社は、令和6年3月期の法人税申告で売上1,000万円を除外し、過少申告していました。令和7年の税務調査でこれが発覚し、追加納付すべき法人税額が350万円と判明。意図的な仮装・隠蔽と認定されました。
適用されるペナルティ:
- 重加算税: 350万円×35% = 122.5万円
- 延滞税も別途発生
もし代表取締役がこの不正行為を主導し、除外した売上金を個人的に流用していて、会社に納税能力がなければ、代表取締役個人が第二次納税義務を負う可能性があります。会社の責任を役員個人に及ぼす、非常に厳しい措置です。
ケース3:繰り返される無申告
フリーランスのCさんは、令和4年分、令和5年分ともに所得税の無申告を指摘され、加算税を課されました。令和6年分も申告せず、再び調査で指摘。納付すべき税額は100万円でした。
適用されるペナルティ:
無申告加算税(10%加重):
- 50万円×25% + 50万円×30% = 12.5万円 + 15万円 = 27.5万円
- 加重がなければ13.5万円で済んだところ、倍以上に!
なぜこんなに厳しくなったの?改正の背景
なぜこのような改正が行われたのでしょうか?
税負担の公平性確保
最も重要な目的は、税負担の公平性を確保すること。きちんと申告・納税している大多数の納税者が、意図的に納税を免れようとする人たちによって不利益を被ることがないように、制度を整備する必要がありました。
特に、高額な所得を得ながら申告しない、あるいは繰り返し無申告を行うといった行為は、公平感を著しく損なうため、より厳しい対応が求められたのです。
悪質な無申告行為の抑止
改正は、悪質な無申告行為を未然に防ぐことを強く意識しています。単に発覚後にペナルティを課すだけでなく、高額な税額に対する税率引き上げ(30%)や、繰り返し行為への加重措置(10%加算)といった厳しい措置をあらかじめ示すことで、「無申告は割に合わない」という認識を広め、納税者に自発的な申告を促す狙いがあります。
経済社会の変化への対応
インターネット取引の拡大などにより、個人・法人を問わず所得を得る手段が多様化し、それに伴い無申告のリスクも増大しています。
例えば、副業やフリーランス、投資、暗号資産、海外取引など、従来の給与所得者とは異なる形態で収入を得る人が増えています。こうした経済社会構造の変化に対応するため、制度の見直しが行われました。
実務上どう対応すればいいの?
では、実際にどう対応すればよいでしょうか?
1. きちんと記帳・証憑管理をする
日々の取引を正確に記録し、領収書やレシートなどの証憑書類をきちんと整理・保存することが基本中の基本です。
これは単に税務上の要請というだけでなく、自分の事業や家計の状況を把握するためにも重要です。特に、令和6年1月1日施行の改正では、税務調査の際に帳簿の提示・提出を拒否したり、帳簿への売上記載が著しく不十分だったりした場合に、ペナルティの加重措置が適用される制度も導入されています。
2. 申告義務を確認する習慣をつける
「私には申告義務はないだろう」と思っていても、実は申告が必要なケースは少なくありません。特に以下のような場合は注意が必要です:
- 副業や兼業がある(年収20万円超)
- 不動産収入がある
- 株式等の譲渡益がある
- 給与収入が2,000万円を超える
- 退職所得がある(特に役員)
- 複数の会社から給与をもらっている
少しでも「申告が必要かも?」と思ったら、税理士などの専門家に相談するのが安心です。
3. 早めに相談・対応する
万が一、申告漏れや無申告に気づいた場合は、決して放置せず、速やかに対応しましょう。
税務署から指摘される前に自主的に申告することで、ペナルティを大幅に軽減できます。「このくらいなら大丈夫だろう」という甘い考えは危険です。
4. デジタル化の波に乗る
GビズID連携によるe-Taxの利便性向上など、税務行政のデジタル化が進んでいます。これらのツールを積極的に活用することで、申告の手間を軽減できるでしょう。
一方で、税務当局もデータ分析能力を向上させており、異なる情報源からのデータ突合などが容易になっています。従来は見過ごされていた可能性のある無申告事案が、発見されやすくなっていることも認識しておく必要があります。
最後に:無申告は「割に合わない」時代に
今回の改正を一言でまとめると、「無申告は割に合わない」ということを明確にした、ということでしょう。
特に重要なのは:
- 高額無申告は要注意: 300万円超の部分には30%の無申告加算税
- 繰り返しは厳禁: 過去2年に無申告加算税を課された場合、さらに10%加重
- 不正行為は高くつく: 仮装・隠蔽があれば40%(繰り返しなら50%)の重加算税
- 自主申告が最善策: 税務署の指摘前に自ら申告すれば、ペナルティは大幅軽減
納税は国民の義務であり、適正な申告・納税は社会の基盤を支えるものです。「知らなかった」では済まされない時代になっていることを、しっかり認識しておきましょう。
当事務所では、無申告対応や税務調査対応、事前の税務相談など、幅広いサービスを提供しております。少しでも不安や疑問があれば、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っておりますので、まずはお電話またはメールでお問い合わせいただければ幸いです。