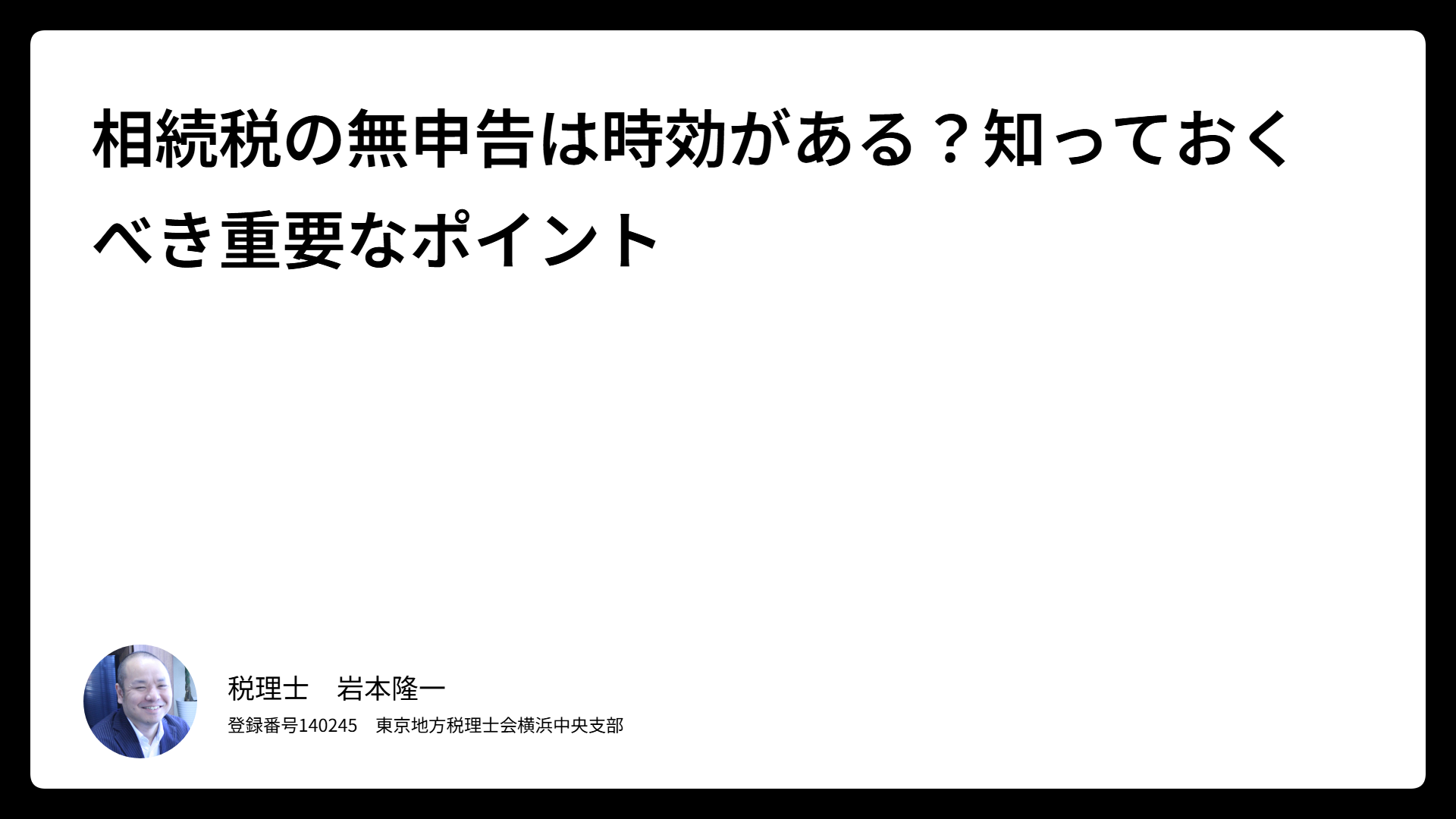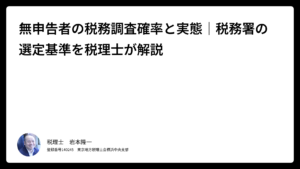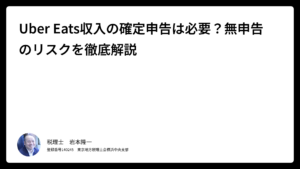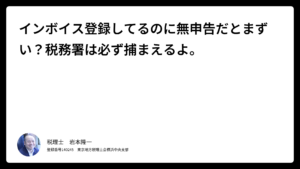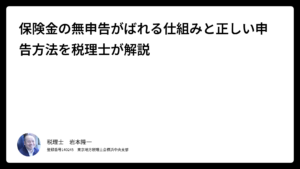「相続税って申告しなくても時効があるから大丈夫でしょ?」
このように考えている方、ちょっと待ってください。税理士として50件ほどの相続税無申告案件を扱ってきた私から言わせていただくと、これは非常に危険な考え方です。
今日は、相続税の無申告と時効について、実際の現場で起きている事例を交えながら、皆さんが知っておくべき重要なポイントをお話しします。
「お墓の前に出ることもできない」クライアントの告白
印象に残っているのは、友人からたまたま相続税の話を聞いて、初めて申告漏れに気がついたというクライアントの話です。
その方は「本当に大きな罪を犯したんじゃないか」と深刻に悩まれていました。なかには「もうお墓の前に出て合わすこともできないよ」と、心から後悔している方もいらっしゃいました。
こうした方々の多くに共通するのは、「まさか自分が申告義務があるなんて知らなかった」ということです。相続税は他人事だと思っていたのに、実際には申告が必要だったというケースが驚くほど多いのです。
相続税の無申告に時効は存在するが…
結論から言うと、相続税の無申告にも時効は存在します。
通常の無申告の場合:5年 悪質な無申告(脱税行為)の場合:7年
この期間が経過すれば、理論上は税務署から追徴されることはありません。しかし、「時効まで待てば大丈夫」と考えていたクライアントで、実際には調査が来てしまって「逃げきれなかった」という話もよく聞きます。
時効の起算点は、本来の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月後)の翌日から計算されるため、思っているより複雑なのです。
現場で見る無申告発覚のリアルなきっかけ
税務署からの問い合わせが最も多いパターンですが、それ以外にも現場では以下のようなきっかけで発覚することがあります:
1. メディアの影響
- テレビで相続税の特集を見た
- 雑誌で相続税の記事を読んだ
2. 人からの情報
- 友人から相続税の話を聞いた
- 知人の相続税体験談を聞いて不安になった
3. 後から発見される財産
- 家を片付けていたら通帳が見つかった
- 知らない不動産があることが判明した
これらのケースでは、本人が「まさか申告が必要だったなんて」と驚くことが多いのです。
最近の税務署は「デジタル」で把握している
最近の税務署の調査手法で変わってきているのは、デジタルでわかることを材料として積極的に使ってくることです。SNSの投稿なども含めて、様々な情報を収集しています。
現代の税務署は、銀行の取引記録、不動産の登記情報、生命保険の支払い情報など、相続財産に関する情報を幅広く収集できる能力を持っています。「バレないだろう」という考えは、もはや通用しない時代になっているのです。
税務調査での「やってはいけない」対応
税務調査で無申告が発覚した際、納税者側がかなり高圧的な態度で臨むケースがありますが、これは絶対にやめてください。
私は常にクライアントに「協力的な体制を取った方がいい」とお伝えしています。相手も人間なので、こちらも誠意を持って対応すれば、向こうも誠意を持って対応してくれるものです。
感情的になったり、攻撃的な態度を取ったりすることは、結果的に自分にとって不利になるだけです。
無申告になりやすい人の特徴
相続の場合、親の財産をちゃんと把握していない人が無申告になりやすい傾向があります。
「申告するほどの財産はないんじゃないか」と思っていても、よくよく確認してみたら後から何かが見つかったというケースは非常に多いです。時には、税務署が見つけてくれるということもあります。
例えば:
- 知らない預金口座を持っていた
- 知らない不動産を持っていた
- 生命保険の受取人になっていた
私が必ずチェックするポイント
相続税の相談を受ける際、私が必ず確認するのは亡くなった方との関係性です。
亡くなった方と親しければ、財産を基本的に把握しているケースが多いです。一方、相続人と仲が悪ければ、財産を把握していないケースが多くなります。
そういう場合は、「財産を見つける手段を見つけてください」とアドバイスして、徹底的な調査をお勧めしています。
無申告が発覚した場合のペナルティ
もし相続税の無申告が税務署に発覚した場合、以下のようなペナルティが課されます:
無申告加算税: 本来の税額に対して15%(50万円を超える部分は20%) 延滞税: 申告期限の翌日から納付日まで、年14.6%または7.3% 重加算税: 意図的に財産を隠していた場合、40%
これらのペナルティを合計すると、本来の税額の2倍以上になることも珍しくありません。
まとめ:時効を待つリスクよりも正しい申告を
相続税の無申告に時効があるからといって、申告をしないでいることは非常にリスクの高い行為です。実際の現場を見ていると、時効が成立する前に発覚するケースがほとんどです。
相続が発生したら、まずは親の財産を正確に把握することから始めましょう。「申告の必要はないだろう」と思い込まず、不安がある場合は専門家に相談することが重要です。
50件の無申告案件を扱ってきた経験から言えるのは、早めの対応が結果的に最もコストが少なく、精神的な負担も軽いということです。
「お墓の前に出ることもできない」という後悔をしないためにも、適切な申告を心がけてください。
税務調査や相続税申告でお困りの方は、お気軽にご相談ください。豊富な経験をもとに、最適な解決策をご提案いたします。