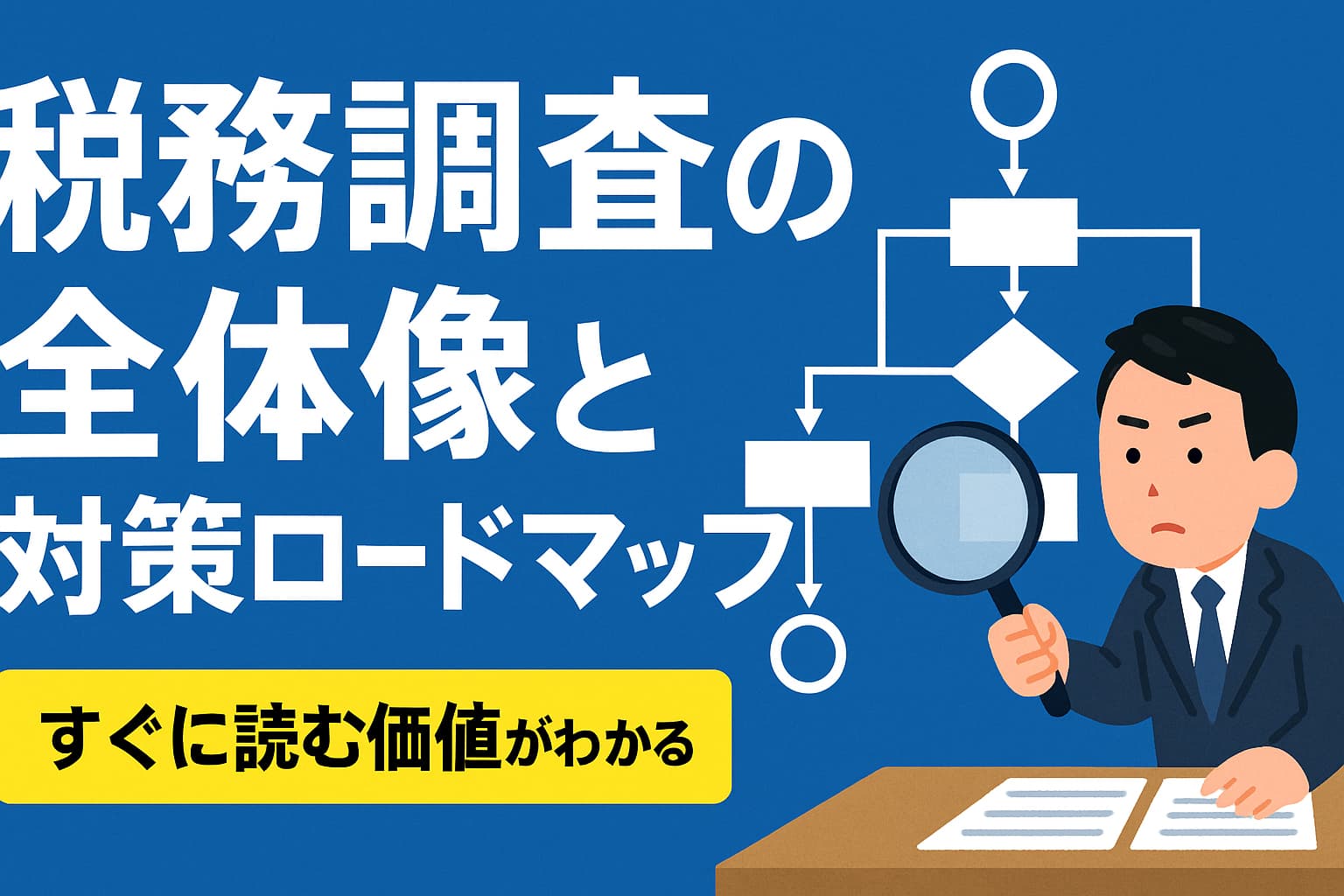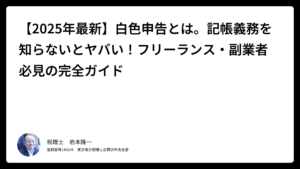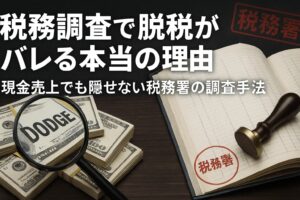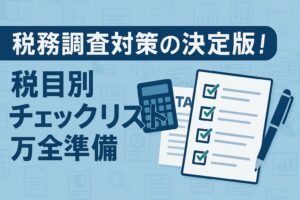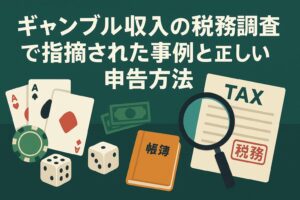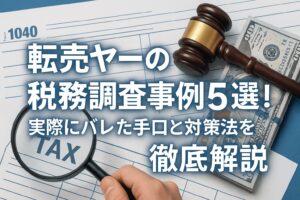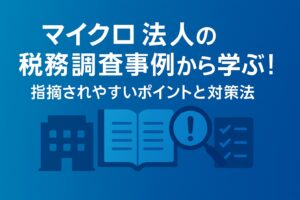みなさんこんにちは、税理士の岩本隆一です。税務調査のご依頼募集中です。
税務調査って聞くと「うわー」ってなりますよね。僕もこの業界に入る前はそうでした。でも実は、ちゃんと全体像を理解して対策を立てれば、そんなに怖いものじゃないんです。今回は「税務調査って結局何なの?」から「具体的にどう対策すればいいの?」まで、ロードマップ形式で解説していきます。
税務調査の種類を理解する:まずは敵を知ろう
税務調査と一口に言っても、実はいろんな種類があります。知らないと「全部同じでしょ?」って思っちゃうんですけど、全然違うんです。
調査主体による分類:誰がやってくるかで大違い
まず調査主体による違いを見てみましょう。
税務署調査が一番よくあるパターンで、これは地元の税務署の職員がやってくるやつです。個人事業主から中小企業まで幅広く対象になります。「近所の税務署のおじさん」って感じですね。
国税局調査というのがあって、これはちょっと格上です。大きめの企業や複雑な取引をやってる会社に来ます。税務署レベルじゃ手に負えない案件って感じ。調査官も専門性が高くて、より厳しい調査が予想されます。
国税庁調査もあるんですが、これはもうエリート中のエリートが担当する超大企業レベルの話なので、普通の人には関係ない世界です。
任意調査 vs 強制調査:「任意」は嘘?
ここが重要なポイント。税務調査には「任意調査」と「強制調査」があります。
任意調査は事前に通知があって、「来月調査に伺います」みたいな感じで始まります。「任意」って名前がついてるから「断れるんでしょ?」って思うかもしれませんが、これが大きな勘違い。実際は拒否すると罰則があるので、実質的には任意じゃありません。ほぼ強制みたいなものです。でも、日程調整とかはある程度できるので、その点では「任意」っぽい部分もあります。
強制調査は、いわゆる「マルサ」による調査です。これは令状を持って突然やってきて、有無を言わさず調査開始。重大な脱税の疑いがある場合のみで、一般の人が遭遇することはほぼありません。ドラマや映画でよく見るやつですね。
調査方法による分類:どうやって調査するか
調査方法による違いも重要です。
実地調査が一番一般的で、これは調査官が実際に会社や事務所に来て、1〜3日かけてじっくり書類をチェックするパターン。帳簿や領収書を実際に見ながら、「これはどういう取引ですか?」みたいな質問をガンガンしてきます。
机上調査というのもあって、これは書面や電話だけで終わる軽いやつです。「この件、ちょっと教えて」みたいなノリで、わざわざ来社することはありません。
簡易な接触というのもあって、これはもう調査って言うより「ちょっとした質問」レベル。電話で「これってどういうこと?」って聞かれる程度です。
反面調査:あなたの取引先にも調査が?
そして忘れちゃいけないのが「反面調査」です。これは直接あなたの会社を調査するんじゃなくて、あなたの取引先に対して行われる調査のこと。
例えば、あなたの会社が A 社に外注費を払ってるとします。税務署は A 社を調査して、「B 社(あなたの会社)から○○円もらってるけど、ちゃんと売上に計上してる?」みたいな確認をするわけです。この時、あなたの会社の取引内容も間接的にチェックされることになります。
反面調査の怖いところは、自分が知らないうちに調査されてることです。取引先から「税務署が来て、御社との取引について聞かれました」って連絡が来て初めて知るパターンが多い。だから、取引先との関係にも影響することがあります。
事前通知の有無による分類
最後に、事前通知があるかどうかによる分類もあります。
事前通知調査は、1〜3週間前に電話で連絡があるパターン。ほとんどの任意調査がこれに該当します。準備時間があるので、書類の整理とかができるのがメリット。
無予告調査は、文字通り予告なしでいきなり来るパターン。現金商売とか、証拠隠滅の可能性が高い業種で行われることが多いです。朝一番にいきなり来られると、本当にびっくりします。
個人と法人で全然違う話
個人事業主やフリーランスの場合と、法人の場合では、調査の性格が全然違います。最近めちゃくちゃ増えてるのが個人向けの調査で、YouTuberとかブロガーとか、昔はなかった職業の人たちがバンバン調査されてます。副業ブームの影響もあって、対象がものすごく広がってるんです。
個人の調査で特によく狙われるのが、収入の計上漏れです。現金でもらったやつとか、副業の分とか、「バレないでしょ」って思ってたやつ。でもバレてます。あと最近多いのが仮想通貨で、「よくわからないから申告してない」って人も多いんですが、これも完全にアウト。経費の按分も要注意で、自宅兼事務所の人とか、車を仕事とプライベート両方で使ってる人は、「なんとなく半分ずつ」とかじゃダメです。ちゃんと根拠が必要。
個人の調査は自宅で行われることが多いんですが、プライベートな部分は調査対象外なので、「家族の書類は関係ないから!」って言えます。当然ですけどね。調査場所も選択肢があって、自宅以外にも税務署に呼び出されたり、税理士事務所でやったりすることもあります。
一方、法人の調査は個人より複雑で、期間も長いし、調査官もガチです。中小企業なら2〜3日で調査官2〜3人というパターンが多いんですが、大企業になると数週間から数ヶ月、専門チームが組まれることもあります。もはや戦争みたいなレベル。
法人で絶対見られるのが売上関係で、売上の計上時期とか、期末の駆け込み売上とか、「決算対策でしょ?」って疑われるやつです。経費の区分も面倒で、交際費と会議費の違いとか、外注費と給与の違いとか、1円間違えても「はい、アウト」みたいな厳しさがあります。役員給与の妥当性も重要で、社長の給与が適正かどうか、高すぎても低すぎてもダメという絶妙なバランスが必要です。
調査の流れを理解する:何が起こるかを知っておこう
税務調査の流れを理解しておくと、心の準備ができます。まず事前通知から始まって、これは調査の1〜3週間前に電話がかかってきます。「来月の何日に調査に伺います」みたいな感じ。この時点で日程調整ができるので、都合の悪い日があれば相談できます。
調査当日は、だいたい午前中に概要説明があって、帳簿の概観をチェックされます。午後からが本格的で、詳細な書類チェックと質疑応答が行われます。調査官は経験豊富なので、問題がありそうなところを効率よく見つけてきます。
調査後は、問題があれば指摘事項の説明があって、問題なければ「是認通知」がもらえます。問題があった場合は修正申告を勧められるので、税理士と相談して対応を決めることになります。
事前対策が9割:日常からできることをやっておこう
税務調査で一番大切なのは、「調査が来てからの対応」じゃなくて「調査が来る前の準備」です。これはマジで重要。日常の記帳から始まって、取引はリアルタイムで記録する、領収書は月別・科目別に整理する、メール添付の請求書とかは電子保存するといった基本的なことから始めましょう。
もう少しレベルを上げると、経費精算ルールを明文化したり、判断に迷うことは税理士に積極的に相談したり、四半期ごとに帳簿をチェックしたりといった中級者向けの対策があります。さらに上級者になると、書面添付制度を活用して調査の回避や縮小を図ったり、電子帳簿保存法に完全対応したりといった高度な対策もあります。
特に最近重要になってるのが電子帳簿保存法への対応で、メールで受け取った請求書とかWebからダウンロードした領収書は、紙じゃなくて電子データで保存する必要があります。これ、意外と多くの企業が対応できてないんですが、調査では必ずチェックされるポイントです。
調査当日の対応:冷静に、でも戦略的に
調査当日は、基本的には冷静に、誠実に対応することが大切です。感情的になったり、嘘をついたりするのは絶対NG。でも何でもかんでも正直に話せばいいってものでもなくて、聞かれたことだけに答える、不明な点は「確認します」と言って即答を避ける、専門的な質問は税理士に任せるといった戦略も必要です。
実践的なコツとしては、どんな質問があって何を提出したかをメモに取っておくこと。後で振り返るときに役立ちます。あと、長時間の集中は判断力を鈍らせるので、適度に休憩を取ることも大切。調査官も人間なので、お茶くらいは出しましょう。
調査後の対応:結果に応じた戦略を
調査の結果、問題がなければ是認通知書がもらえます。これは将来の調査時に有利になるので、大切に保管しておきましょう。軽微な指導があった場合は、素直に改善すればOK。
修正申告が必要な場合は、まず加算税の軽減交渉ができないか検討します。正当な理由があれば主張する価値があります。一括払いが困難な場合は分割納付の相談もできるので、無理は禁物。そして何より大切なのが、同じミスを繰り返さないための対策強化です。
もし税務署の判断に納得できない場合は、不服申立ての手続きもあります。3ヶ月以内なら再調査の請求ができるし、それでもダメなら国税不服審判所への審査請求、最終的には裁判所への訴訟という道もあります。ただし、勝訴率は正直言って低めなので、確固たる証拠と法的根拠が必要です。
業種別の特別対策:自分の業種の特徴を知っておこう
業種によって調査のポイントが違うので、自分の業種の特徴を知っておくことも大切です。現金商売の飲食店や小売業なら、レジデータの保管や仕入れ・在庫管理、従業員への売上除外防止教育が重要。IT・Web系事業なら、電子取引データの管理や外注費と給与の区分、知的財産の適正評価がポイント。不動産業なら、土地建物の時価把握や建設仮勘定の管理、賃貸収入の計上時期が重要になってきます。
どの業種でも共通して言えるのは、業界平均との比較分析をしておくこと。自分の会社の数字が業界平均と大きく乖離してると、調査対象になりやすいんです。異常値があれば事前に理由を説明できるよう準備しておきましょう。
まとめ:予防こそ最強の武器
税務調査は「運が悪かった」で済む話じゃありません。日頃の正確な処理こそが、最強の武器になります。今すぐできることから始めて、少しずつレベルアップしていけば、調査が来ても堂々と対応できるようになります。「備えあれば憂いなし」、これが税務調査との正しい向き合い方です。